
|
|
�C�G�X�ɕ������ƒ������~�a ��~�c�炸����t���ꂸ �����T���^���Ղ�CD���� �����g�i�J�C���S�zCD |

 ���������� |
Danny Grissett "Promise" (Criss Cross : Criss 1281 CD) �@moment's notice �Aautumn nocturne �Bpromise �Cwhere do we go from here �DCambridge place �Eyou must believe in spring �Fon the edge �Geverything happens to me �Heleventh hour Danny Grissett (p) Vincente Archer (b) Kendrick Scott (ds) �Ǖ��ɂ��ď����̃��[�_�[�́C����j���[�E�X�N�[���̏C�m�ے���2000�N�ɏo���̂��C�����N�����@�i��Ńo���[�E�n���X�C�n�[�r�[�E�n���R�b�N�C�P�j�[�E�o������Ɏt�������V�l����B�r���[�E�q�M���Y�̃T�C�h�����Ƃ��ăv�����肵�������͌̋��̃��T���[���X�E�G�Ŋ������Ă��������ł����C2003�N����j���[���[�N���_���ڂ��C���B���Z���g�E�n�[�����O�̃T�C�h�����ƂȂ��Ę^���ɉ����ق��C�g���E�n������W�����E�n�[�h�̘e�Ōo����ς݂܂����B���ݍ��ӂȖʁX�ɂ́C�}�[�J�X�E�X�g���b�N�����h��j�R���X�E�y�C�g����C�`���h�̗�������ތ�m�������B2006�N�ɏo�����̏����[�_�[����C�{���̇H�ɒ��ڂ���C�ނ̃��[�c�͈�ڗđR�ł��傤�B�����ɉe���͂̂ł������}���O�����[�E�~���[�̗�������ށC�]����D�����[�h�E�s�A�m�ł��B������S�ȁC���t�Ƃ̎肷���т��R�C�X�^���_�[�h�Q�ŋύt������������ȍ��̃g���I��B�̐S���Z�I�����łɐV�l���ꂵ�Ă���C���ɓ������d���Ă̗ǂ��ɂ͋����܂����B�~�������C���삪�ǂ������Ă��锽�ʁC���P�肷���Ă��܂��ҋȂɎႳ�����ނ��ƁB�̂��̂⑼�҂̊y�Ȃ̉��߂ɂ͎�̉ۑ肪�c��܂����B����ł��C���ꂾ���̘r������C�܂��傫�ȗь�E�G�ł��H�����ς���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�W��ɋU�薳���B�����f�B�A�X�Œ[���ȃ��[�h�E�s�A�m�����D���ȕ��͊ԈႢ�Ȃ��ڐK��������܂��B���E�ߔՁB |
![]()
| Recommends |
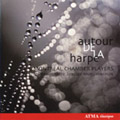 "Sérénade (Roussel) Prélude, Marine et Chanson
(Ropartz) Sonate (Debussy) Introduction et Allegro (Ravel) Quintette No.2
(Koechlin)" (Atma : ACD2 2356) "Sérénade (Roussel) Prélude, Marine et Chanson
(Ropartz) Sonate (Debussy) Introduction et Allegro (Ravel) Quintette No.2
(Koechlin)" (Atma : ACD2 2356)Jennifer Swartz (hrp) Timothy Hutchins (fl) Robert Crowley (cl) Marianne Dugal Jonathan Crow (vln) Neal Gripp (vla) Brian Manker (vc) 1954�N�p�E�B���`�F�X�^�[�B�o�g�̃e�B���V�[�E�n�b�`���X�́C1978�N���烂���g���I�[�����̎�ȃt���[�g�����ƂȂ�C�f���g����i���čŐⒸ���ւƌ��������I�P���x��������B�{�ƂŃt�����X�Â��Ă����Ƃ͂����C�܂������̎�̑啨���C�ߑ�ׂ�����̎����y�ȑI�Ȃ�č���Ă����Ƃ͎v���܂���ł����B�������̎�̋Ȃ����t����̂́C�u���O�N��H�v�Ɩڂ��_�ɂȂ���X�����S�B�ނقǂ̑啨���^�������Ƃ��������ŏ[���j���[�X�ł����C�ߑ�t�@���̍w���ΏۂƂȂ蓾��ł��傤�B�����Ƃ����r�����́C�X�����_�[�œs��I�B���̃C���[�W���ʂ����̍����Z�ʂŁu�ł���OL�v�Ԃ���A�s�[������B�B��C�C�ɂȂ�_������Ƃ���C�Z�ʂƂ��������ȉ��߂ł����B����݂̃��p���c���ɋ����܂��ƁC���y�͂͑傫�߂̃A�S�[�M�N�ŁC�����ߑ��B�e���|�x�����Ŋԉ��т��Ă��܂������ۂ��C���y�͂ł͖������ɍS�肷���C�f���i�[�~�N�ş������C���o�����Ƃ��邽�߁C�₽���肷���Ă��܂��B�h�r���b�V�[���C�X���[�̉����ɕω��������C���Y���̏��������d�����y�͂�C���߂̃e���|����͂��{���q�Ȃ��߁C�ّ��ɂ��������Ă��܂����y�͕ӂ�͍D�݂̕������]�n���c���ł��傤�B����ł��C�͂��������M���ɁC��y�A���T���u���Ƃ��Ă̋Z�ʂ͍ŏ�N���X�B���ꂼ��ɓ���c���������̘^���̂قƂ�ǂ��y�X�ƒ���������Ԃ�Ɋ��Q�B�u�J�i�_�̓c�ɂɏZ��ł閳�����t�ƂɁC������Ƃ��f�B�O������V�嗤�ł܂�q�v�Ȉ�ۂ����Ȃ�����ATMA�ɁC���߂ėǂ��Ӗ��ŗ����܂����B���������� |
 Frank Martin "Cello Concerto / The Four Elements" (Doron : DRC
3044) Frank Martin "Cello Concerto / The Four Elements" (Doron : DRC
3044)Bernard Haitink (cond) Jean Decroos (vc) Concertgeboworkest Amsterdam �x�߂̃e���|���Ƃ�C�\�����������ƒ͂ގ����Ȏw���Ńs�J�C�`�̐M�������ւ�n�C�e�B���N����B�}���^����CD�Ȃ�ďo���Ă�����ł��˂��B�������C���������ƂɁw�l���f�x�������Ă�B�O��̂Ȃ��n�C�e�B���N�̎w���ƃR���Z���g�w�{�E�̌��ł���ȉ��ڂ���̂́C�[���w�����@���肦��ł��傤�B�ȂɂԂ�1970�N�̃��C�u���t�B�����ŕ�������P�����͂قƂ�Ǐh���ł��B�����C�q�Ȃ͂��Ȃ�Â��ŃC�����Ɨ���u�Ԃ͏��Ȃ��ł����C�����ȍ\���ɑ���w���҂̌��ʂ��̗ǂ����i�Ⴂ�B�҂��҂��̃f�W�^���^���Ř^��ꂽ�o�[�����g�̘A���^���ł��[�������߂Ă�����ł����C�ЂƂ��ь��̎w���_�Œ����Ă��܂��ƁC��͂�����͂��Ⴂ�܂��B�������w�`�F�����t�ȁx�������ł��˂��B�`�F���X�g�̃h�N���[�X��1944�N�J�����܂�̕��l�B�p�����y�@�Ńg�D���g�D���G�ƃi���@���Ɋw�сC������ƃf���I�������B1951�N�̃N���C�X���[���J�U���X���ہC1959�N�̃W���l�[�����ۂł́C�v�w�ŏo�ꂵ�ėD���������͎ҁB���̌�C1962�N�ɃR���Z���g�w�{�E�ǂ̎�ȃ`�F���X�g�ƂȂ��ăI�����_�ֈڏZ���C�A���X�e���_�����y�@�ŋ��ڂ������Ă���悤�ł��B���F�͕��l�Ƃ͎v���ʂقǍ����s���Ɖ����B�������C���̌�����[���ɔ����C�����ꂵ���͊����܂���B�I�P�Ƃ��ǂ��C�����ȃ��}���h�ǂ̂��ꡂ��ɗǂ��C�������̓I�P�E�̃C�`���[���ƃR���Z���g�w�{�E�ǁB1970�N��̎�����l����C�����܂Ŕ����ȓ��ꉉ�ڂ̘^���́C�قƂ�ǂȂ���Ȃ��ł��傤���B���E�߂ł��B���������� |
 Jean Wiener "Concerto pour Accordéon et Orchestre / Sonate
pour Violoncelle et Piano / Concert pour Orchestre et un Piano Principal"
(Arion : ARN 68186) Jean Wiener "Concerto pour Accordéon et Orchestre / Sonate
pour Violoncelle et Piano / Concert pour Orchestre et un Piano Principal"
(Arion : ARN 68186)Gilbert Roussel (accd) Jean Wiener, Jacqueline Robin (p) Pierre Pénassou (vc) André Girard (cond) unknown Orchestra �̋ȏW�Ǝ��쎩���̃s�A�m�ȏW���炢�͑��݂�m���Ă������̂́C�܂����nj��y�Ȃ��o�Ă���Ƃ͎v��Ȃ��������B�G�l���B���܂��ɂ��ꂪ�s�J�C�`�N�Ɨ��Ă͂��Љ�Ȃ��킯�ɂ͍s���܂���B�t�����Z�Ƀv�[�����N���Ȃ���������悤�ȋ}�����ƁC�~���[��N�̏���Ȃ���̊Ɋy�͂̊Ԃɉ������f�w�ɁC�p���̕������̙R���ȃA���j���C�����߂��Ă���B�����Ď���̋Â炳�ꂽ���ʂł͂Ȃ����̂́C�Ȃɂ��ėv�͂�������Ɖ��������nj��y�����a���F���őf���炵���B�A�R�[�f�B�I���ƃI�P�Ȃ�č����̂��Ǝv���Ă܂������C���ꂪ�p���̏H�����I�݂ɑ����Ď��ɂ������ł����C�Z�l�g�����ɂ����\�i�^���C�ߑ�ƌ���̃o�����X���o�����ɑf���炵��������B���������ƂɃ\���X�g�̉��t�������ݍ������Ɨ��Ă���B�R���Z�[���Ŏ������I�����Ȏ҂́C�m���ɑ����p�b�Z�[�W�ł͖��Ղ���Ƃ��������܂��B�������C�^����������75�˂������͂��B���ꂻ�ꂪ�M�����Ȃ��قǂӂ��悩�ʼn~�݂̂���C���b�`�ȑŌ��Ɋ��Q�B�`�F���E�\�i�^�̓�l����肢�����C�^����1970�N�㏉���ɂ��Ă͔j�i�ɐ���ł����ł��˂��B���ꂾ���ɁC�B��c�O�������̂́C�Ȃ�����̖��̏�����Ă��Ȃ���I�[�P�X�g���B�����ăh�w�^�ł͂Ȃ��Ǝv����ł����C���Ƃ������ӎv�����ꂳ��Ă��Ȃ��Ƃ������C�A�[�e�B�L�����[�V�����������Ă��܂���˂��B�W�߂�������ł��傤���B�ܑ̂Ȃ��B���������� |
 Othmar Schoeck "Konzert, op.61 / Sommernacht, op.58" (Claves : CD 50-8502) Othmar Schoeck "Konzert, op.61 / Sommernacht, op.58" (Claves : CD 50-8502)Johannes Goritzki (cond, vc) Deutsche Kammerakademie Neuss �V���[�x���g�ւ̓��ۂƃV�F�[���x���N�̎��㐫���C��l�̒��őg����C�s�v�c�ȋ�ɗ��ݍ������l�Ԃ��������y���C�V�F�b�N����ł��B�h�C�c�L�����y�͍D�݂ɍ���Ȃ��ɂ�������炸�C�s�v�c�Ƃ��̐l�̉��y�͋C�ɂȂ�C������Ɣ����Ă��܂��܂��B�{�Ղ͂Ђƍ��C�����n���Ƃ̃W�F�b�N�����ƕ���ŁC�V�F�b�N�̎�v��i��^�����Ă����N���x�X����o�����̂ŁC�ӔN�̑�\��Ƃ����w�Ă̖�x�^�B�����N���x�X����o���I�P�t�т̉̋Ȃł́C�I�l�Q�����т�����̋C��������ɋ����܂������C�ʐl�̔@�������Ȃ��̓�҂��Ă��C��������̒E�p���u�������̂́C��C�̎��肾�����̂ł��傤�B���݂��݂ƃG���W�A�b�N�ɋՐ��ɐG��Ă��������́C������Ȃ��V���[�x���g��]�������ނ̔������t�F�`�Ԃ����l�B�������C�����I�Ȕ����t���[�Y���قƂ�ǎg��ʂ܂܂ǂ��܂ł��~������������ƁC���̗\�����ɂ߂č���ȓ]���Ŏx�z����鋦�t�Ȃ́C�h�C�c�E���[�g���ߑ�̖ڂōĉ��߂���ނ̎������C�܂��܂��ƕ����B�ƃ��}���h���o���_�ɁC����̌�@�W��������ȉƂƂ����C���E�G�ɂ����N�[��}�j���[�������܂������C�₽�璷��Ŋ����I�C�������͂ݏ��̂Ȃ��قǒ���Ȏ��Ƃ����_�ł́C�ނ��ɂ߂ċ߂��Ƃ���ɂ����̂ł��傤�B�����Ă��w�Ă̖�x�́C�d�������R���ȃT�r�̐߉��C�܂�ʼnp���ߑ�̍�ȉƂ��Ǝv���قǏ�L���B�Â��ɗ����t�����L�X�g�Ƃ͏�������������u���C�s��ȃ��O�l���Y���Ɉ��邱�Ƃ��Ȃ��C���T�ݐ[���֗~�I�Ƀ��}���X�����Q���}�����̃��}���h���w���C�F�Z���o�����i�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������C���̊nj��y�̉��ȂƁC�ו��̖щH�������C�ɂȂ�u�Ԃ�������̂́C���t�͑����ėD�G�B�����̃l�E�X�����A�J�f�~�[���C�}���R�n�̃I�P���͐��i�D�G�ȉ��t�ŃS���c�L����̉��X�����`�F�����x���܂��B���������� |
 Claude Debussy "Sonate pour Flûte, Alto et Harpe / Sonate pour Violoncelle et Piano / Sonate pour Violon et Piano / Danse Sacrée et Profane / Rhapsody" (Pearl : GEMM CD 9348) Claude Debussy "Sonate pour Flûte, Alto et Harpe / Sonate pour Violoncelle et Piano / Sonate pour Violon et Piano / Danse Sacrée et Profane / Rhapsody" (Pearl : GEMM CD 9348)Marcel Moyse (fl) Eugene Ginot (vla) Lily Laskine (hrp) Maurice Marechal (vc) Robert Casadesus (p) Jacques Thibaud (vln) Alfred Cortot (p) Maurice Viard (as) Piero Coppola (cond) �X�e���I���ȑO�̒��쌠�ꉹ�����f�W�^�������邱�ƂɊ|���Ă͂҂������̉pPearl����o���{�Ղ́C�h�r���b�V�[�^���j���t�������\��������t������ł����ƃJ�b�v�����O�B��x�͒ʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ǂł͂���܂����̂ŁC���̋@��Ɏ���݂��Ă݂邱�Ƃɒv���܂����B������C���l�Ɉ��̃t�@�������̂������B����Ɨ��V�̈قȂ�C���߂̃e���|���Ɉ�a��������������̂́C��y���̂Ɋւ��Ă͑����Ĕ��Ƀ��x���������ł��B�O�d�t�\�i�^�́C�����炳�܂ȓ����r�u���[�g���@�ɂ��C����̂��̂ɔ�׃Z�J�Z�J�Ɛّ��ȃ��m���������L�̕Ȃ͂�����̂́C�v���v���œI�m�ɑ}������郊�^���_���h���Ȃɂ��Ȃ₩�ȋȐ�����^���ċْ�����ێ��B���炭ꡂ��ɗL���Ř^�����ǂ��C�����p�����t���[�g�𐁂����G���[�g�Ղ����C�����n���������ċX�����Ǝv���܂��B�����ȃe�B�{�[�ƃR���g�[�͍̂��߂Ē����܂������C������͂���ɑ傫���e���|��h�炵�ă_�C�i�~�b�N�����₩�Ȕ����B�����I�ȏ���O�ɁC���ꂾ�����������t������Ă����Ƃ́C�Ɩڂ��_�ɂȂ�܂����B���ꂾ���Ɏc�O�Ȃ̂́C�d���Ȃ��Ƃ͂�����͂舳�|�I�Ɉ����^���B�S�҂ɃW���p�`����郂�m�����̉����́C���ꂾ���Ńh�r���b�V�[����҂̂قƂ�ǂ����₷��ɏ[���B���ꖜ�l�ɂ����߂Ƃ͍s���܂��܂��B������܂��C�e�X�̋Ȃ́u���^�\�ہv���]���Ɍ`������C���ݘ_�I�ȉ��t�̏o���ƌo���_�I�ȉ��̑��Ƃ���ʂ��Ė����߂�悤�ɂȂ����������̉��ՂƂ������ƂɂȂ�ł��傤�˂��B���������� |
 Arthur Honegger "Le Chant de Nigamon / Pastoral d'Été
/ Symphonie No.2 / Symphonie No.5" (Auvidis Valois : V 4831) Arthur Honegger "Le Chant de Nigamon / Pastoral d'Été
/ Symphonie No.2 / Symphonie No.5" (Auvidis Valois : V 4831)Charles Munch (cond) Orchestre National de France �l�I�ɂ́C�I�P�̕s�o���������C�I�l�Q�����ł���肭�U���Ă����̂̓Z���W���E�{�h���Ǝv���܂��B�������C���炭��ʂɁC�I�l�Q�������Ȃ̉��҂Ƃ��čł������]���ɂ��Ă���ł��낤�l���̓J���������C�{�Ղ̎���~�����V������ł��傤�B���̂����݂��Ȃ������ނ̃I�l�Q���S�W�B����͕̂��^�̂甄������B�C���C�����҂��Ă݂܂������Ƃ��Ƃ��䖝�ł����C�o���ő����悤�ƒ��߂Ĕ���������B�����Ăт�����ʎ蔠�C�{�I�l�Q���I�W�͑S�ă��C�u�^���B�Q�҂̌����Ȃ͊e�X�X�y�C���ƃt�B�������h�ł̘^���ŁC���܂��Ƀ��m�����B1964�N�^���Ȃ̂ɌÏL�����ƁB�����J�b�v����������킯�ł���E�E�B�w�j�K�����̉́x������Ȃ̉��t�̓{�h�����_�C�i�~�b�N�Ő��i�͂�����C����́w�����ȑ�S�ԁx�̘^���Ŏ��������z�Ɠ����B���߂̃e���|�ł���Ȃ���I�݂Ƀ����n���𗘂����C������ّ����ɕς��ʂ悤�ő���z�����Ȃ���C���������Ɛ��i�͂����ĐS��h�݂͂ɂ���B�ɂ߂Č��ʂ��̗ǂ����߂ɎQ��܂����B����ɋ������̂́w�Ă̖q�́x�ɂ�����C�ӊO�ȂقǗǂ����Ȃꂽ�̂��B���ς�炸�����ς�Ƒ��߂̃e���|�ł��т��тƐU���Ă���ɂ�������炸�C���肪�[���ʊ��L���B�v���Ńs�V�s�V���Ɣ�����߂ċْ����ƉA�e�����C�������_�����ّ�����^���Ȃ��B�{�[�h�̖��^���ȊO�ŁC���߂Ċ��S���鉉�t���܂����B�����Ȃ�ƕԂ��Ԃ����q�h�C�^�����c�O�B�ꉞ�m�C�Y���������͉����Ă���C�W���p�`���͂���܂���ǁC�����ʂł̕s���͂�����Ƃ�����ł��B���ꂾ���U���Ȃ�C�Ȃ�ŏW���^�����Ă���Ȃ�������E�E�B�s�A�j�X�g�̃��T�C�^���M�ɂ��������̂���������ł��傤���B�ɂ�������ł��E�E�B���������� |
 Lucien Durosoir "Sonate en La Mineur / Oisillon Bleu / Cinq Aquarelles
/ Chant Élégiaque / Prière à Marie / Lucien
Durosoir, en 1950" (Alpha : 105) Lucien Durosoir "Sonate en La Mineur / Oisillon Bleu / Cinq Aquarelles
/ Chant Élégiaque / Prière à Marie / Lucien
Durosoir, en 1950" (Alpha : 105)Geneviève Laurenceau (vln) Lorène de Ratuld (p) ���炭���ɏo��̂͏��߂Ẵf�����]���[���́C�O���I�����Ɋ��������@�C�I�����e���B�p�����y�@�Ŋw�Ԃ��C���t�ƂƂ��Ă͂��̌�w���A�q���̗����g�ރh�C�c���B��ꎟ��풆�̓J�v���ƃ}���V�����C�A�����E�������[�k�̂S�l�Ō��y�l�d�t�c��g��ł��������ȁB�����`�I��Ђ̂��ƂœƑt�҂Ƃ��Ă̓�����߂��ނ́C�g�D���k�~�[����E�W�F�[�k�E�R�[���X�ɏA���č�ȋZ�@���C���B���̓p���𗣂�ē앧�ɏZ�݁C��Ȋ��������Ȃ���]���𑗂����͗l�ł��B�ނ͊y�����o�ł���C�͂��炳��Ȃ��C���q�̃����b�N����ɂ��C�܂��Ɂu�Ĕ����v���ꂽ�`�ƂȂ�܂����B�{�Ղ͂��̋M�d�ȕ����㉉�ՂƂ����킯�ł��B���@�I�ɂ͊��S�Ƀ|�X�g�E�t�����L�X�g�B���A���Ղ̑т��A�W��قǃh�r���b�V�X�g�I�ł��g�D���k�~�[���I�ł��C�J�v���I�ł��Ȃ��C�ނ��냆�j�]���ƃg����������̂Ƃ��Ӑ}�I�ɔ��߂�ꂽ�a���̓��t���ƁC���}���`�b�N�Ȏ�����̓��Ȃ��Ȃ��Ƃ���ȂǁC�~�S�̊�y�ɒʂ���Ƃ��낪����ł��傤���B�t�����L�Y���̗�������ށC�������^�̓]�����}���h���@�C�I�����ȏW�E�E�Ǝv���C�����߂�l�͏��Ȃ��Ȃ��ł��傤�B�{�Ղ̔��_�́C���t�̔��킳�B�����̃������\�[���j��1977�N�X�g���X�u�����܂�B�����[�x�b�N�y�уR�����k���y�@�Ŋw�̂��C���b�e���_�����y�@�ŃJ���g���t�Ɏt���B���ۓI�Ȏ�ܗ��͖R�����C2001�N�Ƀ����F���E�A�J�f�~�[����ŗD�G�܂����炢�C���N�̃A�_�~���c�R���N�[���łT�ʂɂȂ��Ă��邭�炢�ł����C����ȃV���{�߂̌o�����R�̂悤�ɗǂ��̂����������Ȃ����Ă���Ǝv���܂��B���������� |
 Joly Braga-Santos "Concerto for Strings in D / Sinfonietta for Strings
/ Variations Concertante for Strings and Harp / Concerto for Violin, Cello,
Strings and Harp" (Marco Polo : 8.225186) Joly Braga-Santos "Concerto for Strings in D / Sinfonietta for Strings
/ Variations Concertante for Strings and Harp / Concerto for Violin, Cello,
Strings and Harp" (Marco Polo : 8.225186)Alvaro Cassuto (cond) Bradley Creswick (vln) Alexander Somov (vc) Sue Blair (hrp) Northern Sinfonia �W�����[�E�u���K���T���g�X��1924�N���X�{���o�g�B���܂�L���l���Ȃ��|���g�K���ł́C���炭�ł��ĕ]������Ă���l���̈�l�ł��傤�B���ł��쉢�̃V�x���E�X�ƌĂ�Ă���Ƃ����Ȃ��Ƃ��B����Ȑ���ς�������1951�N�̌��y���t�Ȃ��܂��ƁC�Ȃ�قlj��������`���̊ɑt���ɂ����鏖��͊m���ɂ�����ۂ������m��Ȃ��B�V�ÓT�I�ȕM�v���Ƃ�Ȃ�����C���ォ��M�����Ȃ��قlj������ێ�I�B�쉢�̍�ȉƂȂ��炻��炵���|���g�K���L���͂قƂ�ǂȂ��C�a�m�C���̃X�m�r�Y�����Ȃ��Ƃ������C�p���ߑ�̎��Œ����Ă����܂��a���͊����Ȃ��ł��傤�B�������C1963�N�ɏ����ꂽ�������Ȃł́C�����v���������@�^�ρB�����K��̟T�X���������ł����ƃI�l�Q���I�ɂȂ�C�����ɖ��w�L�ۏo���̃I�u���K�[�h���t���B1967�N�̕ϑt�ȂɂȂ�Ƃ���Ɍ��㉹�y�L���Z���Ȃ�C�����K�~���^�����a�̜늳�����炩�ƂȂ�܂��B1960�N�ӂ�����ɁC�O�ƌ��ł��Ȃ�앗���Ⴄ�悤�ŁC���ӂ��K�v�����m��܂���B���҂ɋ��ʂ��Ă���̂́C��������������ێ�����V�ÓT�I�ȗ֊s�ł��傤���B���ɒ�t���̓��t���͏�肢�ł��˂��B���ꂪ�ނ̉��y�̊��𐬂����ӎ���������ł��傤�B�w���҂���炩�ȃ^�C�v�Ȃ�ł��傤���B���㕗�ɂȂ�����N�̍�i�𒆐S�ɍו��̕s�������U���������̂́C�I�P�͓����x�������т��тƂ������ߍ\����I�m�ɍČ��O�B�u�I�I�b�C�}���R���ꂵ�Ă�I�v�Ɗ��Q���ǂ�����Ɖ��̂��Ƃ͂Ȃ��C������݂̃m�[�U���E�V���t�H�j�A�ł����B�������� |
 Joseph Jongen "Sonate / Aria / Moto Perpetuo / Dans la Douceur des
Pins / Caprice - Impromptu / Habanera / Feuille d'Album / Valse" (Phædra
: 92030) Joseph Jongen "Sonate / Aria / Moto Perpetuo / Dans la Douceur des
Pins / Caprice - Impromptu / Habanera / Feuille d'Album / Valse" (Phædra
: 92030)Karel Steylaerts (vc) Piet Kuijken (p) �u�t�����h���̑�n�Ɂv�Ƒ肵�C�x���M�[�ߑ�̖�����Ɣ��@�ɖz������f�G�Ȓn���ƃt�F�[�h���B���̑�30�e�Ƃ���2002�N�ɏo���{�Ղ́C���ȑŗ����S�W�������ɓn���Ď�ʑŎ҃N���X�̖����W�����Q�����������`�F���Ȃ�S�W���B���}���h�I�������Ƀh�r���b�V�[�O���̘a�����o��▭�Ƀu�����h���C�j��ƍč\�z����ł͂Ȃ��C�ߋ��̌�@�̊g������ߑ㉹�y�̃|�W�e�B�u�Ȕ��W���u��������Ȏ҂̎p�����C���̂܂܍ڂ������ȑ����ł��B�Ȃɕ��吂���s�S���҂͖{�T�C�g�{���֎~�I����ȐM�Ҋۏo���̖\���������Ղ��{�ՁC�c��S�͉��t�Z�ʂ̈�_�ł��傤�B�`�F���X�g�̓u�����b�Z�����y�@�ŃJ�����E�V���~�b�c�Ɏt�����C�����y�ƃ`�F���̗��ۂŏ܂�������đ��ƁB���̌�R���[�j���ł��������������ŁC�x���M�[���c������Ẫe�k�[�g�t�ɓ��܂Ȃ��������Ƃ�����Ƃ��B�\���X�g�Ƃ��Ă͒m���x���Ȃ���C�n�C�y���I���ɉ��߂������h�r���b�V�[����F���̎O�d�t�ȏW�𐁂����t�����X�^���E�g���I�̃����o�[�ƕ����C�g�����o������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�{�Ղł̉��F�̓L�R���ۂ����Y���C�����������Œ������ڂ̋|�e������������u�������v�ł͋Z�p�I�ɂ��Ȃ�h�����B�X���[�����߂ɏ�������鍱�����炵�̂Ȃ����t���V�ɂ���̋^�╄�͂��܂�����ǁC�S�W���̐G�ꍞ�݂ŏ[�����E�B�h�E�O�[�g���Ɏt�������s�A�m���y�_�����O�����e��ŁC�^�w���܂ߎt���̈̑傳������������d�オ��Ƃ͂����C�[���Ɍ����Ȃ����Ă���Ǝv���܂��B�ނ���{�Ղ̏ꍇ�C�^���̏����̂ق������t���V���{����������v���Ƃ��ė����Ă邩���B�t�F�[�h������E�E���`������Ƙ^���C���Ƃ����܂��傤��H�������� |
 Georges Auric "Orphée / Complainte d'Eurydice / Les Parents
Terribles / Thomas l'Imposteur / Ruy Blas" (Marco Polo : 8.225066) Georges Auric "Orphée / Complainte d'Eurydice / Les Parents
Terribles / Thomas l'Imposteur / Ruy Blas" (Marco Polo : 8.225066)Adriano (cond) Vera Rasková (fl) Jacques Tchamkerten (ondes) Slovak Radio Symphony Orchestra �W�����E�E�B���A���X�ȉ������ꕔ�̗�O�������āC�N���V�b�N�̐��E�ł��ʗp����r���������f�批�y�̏����肪�قڎ��ł�������C�Z�l�g�E�G���������ĉf�批�y�������Ă������\�N�O�̊y�E�́C�e�E�̍˔\���ӑR�Ɠ�����������ʔ�������ł����B���b�N�ł�����������1970�N��ł����B�y�d�̍ːl���ɂ������Ȃ��˔\�������Ȃ��C�w�i���y�Ƃ��ė����������Ă��������̉f��t�@�����ґ����ł��˂��B�Z�l�g�̒��ł��ł��o�J�x�������C���ӂƓŋC�ɖ����������t�������邱�ƂɊ|���Ă͓V�˓I�ȍ˔\������I�[���b�N�B�ϋɓI�Ɏ��L���C�ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ȃ�Ȃ��ނ��C�ǂ������킯���nj��y�C������f�批�y�ɂȂ�ƕʐl�̔@���u�܂Ƃ��v�ȍ�ȉƂɂȂ邩�畎��Ȃ��B1998�N�ɘ^�����ꂽ�{�Ղł́C���炭�^���������ł��낤�w�I���t�F�[�x���n�߁C�ނ̉f�批�y�T�т����^�B�킴�Ƃ���Ă�Ƃ����v���Ȃ��s���a���Ƃ����Ƃ傤�Ȓ���ŁC������̃}�]�x�������Ă͍�������C���̂łԂ̃t�����X�l�ƁC���p���c��h�~���[�̓c�ɏ��h�r���b�V�[�I�ȑ@�טa�����I�݂ɐD������āC���݂��݂Ƃ����������l����{�Ղ̔ނ�����l���Ƃ́C����M�����Ȃ��ł���܂��傤�B�ȂɂԂ�f�批�y�ł��̂ŁC�N���]���\���̈�ѐ��͊ɂȂ�C���������Δw�i���y���L�̃p�b�`���[�N�L���͐@���Ȃ���ł����C�������������Ă��C�ނ��o�J�̉��ʂ̗��ɉB���������n�B�̃I�[�P�X�g���[�^�[�Ԃ�͑����ɁB���Ɂw�I���t�F�[�x�͑f���炵���C��\��̖��ɒp���Ȃ�������Ǝv���܂��B�c�O�Ȃ̂́C����ς�ו��̔��������킸���^���Ă��܂��I�P�ł����B����ł��X�����@�N�����͂܂��ł�����B�܂��C�䖝�ł��䖝�i��j�B�������� |
 "Suite (D'Indy) Quintet (Martin) Prélude, Recitatif, et Variations
(Duruflé) Sextuor (Poulenc)" (Premier Recordings : PRCD 1032) "Suite (D'Indy) Quintet (Martin) Prélude, Recitatif, et Variations
(Duruflé) Sextuor (Poulenc)" (Premier Recordings : PRCD 1032)New Jersey Chamber Music Society �����Ĉ������t�ł͂Ȃ����C�ǂ����t�Ƃ����������ɂȂ��N���V�R�̘^���ł̂ݔF�m���Ă���f�����t���B��̎����y��i�w�O�t�ȁC�����ƕϑt�x�B���ɉ��������̂��Ǝv���Ă��܂�����C�����J�b�v�����O�Ř^���Ă����ȃA���T���u�������܂����B�R���z���g���C�v�[�����N�̘Z�d�t�ȊO��1993�N�ɏo���{�Ղ��S�����E���^�������������ȁB�o���b�N�I�Ȏ��X���C�y�₩�ɓ]������ӊ��_���f�B���n���ȉ��i�ł����C�}���^���͂т����肷��قǒ��������Ăȕێ�I���}���h���@�ƁC��������i���ǂ��ȑ����B�I�҂̌�����̍����ɖj�ɂނ̂��ւ����܂���ł����B�����C���̍��������ɘr���t���Ă��Ȃ����̔���B�l�����������������̂�B���t����̓j���[�W���[�W�[�����y����Ȃ�ʁX�B�B���c��̏����Ċ������Ă��邻���ȁB�}�C�i�[�l���@��N�����C�ɂȂ�̂́C����ς莩����������ĂȂ��l�Ƃ����̂͐��̏�ł��āB���ǂ��E�F�u�T�C�g�̈���瑶�݂��Ȃ��̂������C�i�N�\�X���т�����̉��t�Z�ʁB�s�b�`�����������ڂ��Ȃ��C�������̃r�u���[�g�C���ܗ���C���̃t���[�g�C�^�b�`���Y�킾���Ǎו����ŋC���̃s�A�m�ƁC�n�R���������_�B�ɂ�������炸�C�M�ӈ�ŏ����ȋZ�ʂ����W���C���蕨���ЂƂz���グ�邻�̐S�ӋC�ɂ͊��܁B�u���̌�����������^�����悤�ȏW�����n������������āC���i����D���ȏ��s�����邠�����̋Ր����h���B�����̗܂����傿���܂��B�����f�����t����B����Ȃɗǂ��ȏ������̂ɁB���Ń��N�ȉ��t���炵�Ă��炦�Ȃ��̂��C�N�́B�������� |
 Lodewijk Mortelmans "Dageraad en Zonsopgang / Mignon / Morgenstemming
/ Gelios / In Memoriam / Mythe der Lente" (Phaedra : 92033) Lodewijk Mortelmans "Dageraad en Zonsopgang / Mignon / Morgenstemming
/ Gelios / In Memoriam / Mythe der Lente" (Phaedra : 92033)Nina Stemme (sop) Zsolt Hamar, Fernand Terby (cond) Flemish Choir and Flemish Radio Orchestra : BRTN Philharmonic Orchestra-Brussels ���炭��i�W��^�ʖڂɔ����̂͏��߂Ă���Ȃ����Ǝv���郍�h�E�F�[�N�E�����e���}���X�́C1868�N�A���g���[�v���܂�B1893�N�Ƀx���M�[�E���[�}��܂���܂��C1901�N����1924�N�܂ʼn����t�����h�����y�@�őΈʖ@�ƃt�[�K�̋��ڂ����邩�����C1903�N�ɃA���g���[�v�̐V���t����n�݂�����w���҂ƂȂ�ȂǁC�����ʂɊ��܂����B�ނ́u���Ґ�����̎R�ȍ�ȉƁv�ȂǂƂ����L��̂��L��Ȃ��̂��ǂ�������ʈٖ��������C��ێ�`�̉e����������}���h��@�ɏ�����Ă���炵���s�A�m�Ȃł̂ݕ]������Ă���B�܂�Ƃ����Ґ��̖{�Ղ́C����Δނ̍ł��_���ȂƂ�����Ƃ肠������i�Ƃ������ƂɂȂ�܂��E�E�Ƃ����s���ȏ����o���ŋC�Â������N�͂������B�ɒB�Ɍ����ǂ�ł܂���ȁB�i�N�\�X��p�B���O�~���l���n�o�����̉e�������BRTN�ȉ��t�w���\�킸�C�D�т����Ă݂܂������C���g�͂Ƃ����Ώ����Ⴄ�قǓƉ����B�{�Ƃ��͑����f���p���N�I�ȟ������C������C��r�I��N�́w�C���E�������A���x�ӂ�̓|�X�g�ɂȂ��ʃ��}���e�B�X�g�̘g�Ŗ����߂���̂́C��{�̓V���[�}���C�u���[���X�Ƀ��O�i�[�̑�������������ƃ��}���h�̒����B�X�������꒲�Ń��}���X����邱�̍�ȉƂ����ێ�`�̕З�k����낤�Ƃ����̂́C�r����������Ɣ��˂Ȃ�܂���B���t�͂܂��܂��B�����s�[���Ŕ��������e���ł����˂��B�������� |
 Joaquin Turina "Sonata No.1 op.51 / Sonata No.2 op.82 / Sonata Espanola
/ Homenaje a Navarra, op.132 / Variaciones Clasicas / Euterpe, op.93"
(Meridian : CDE 84430) Joaquin Turina "Sonata No.1 op.51 / Sonata No.2 op.82 / Sonata Espanola
/ Homenaje a Navarra, op.132 / Variaciones Clasicas / Euterpe, op.93"
(Meridian : CDE 84430)Roland Roberts (vln) Miyako Hashimoto (p) �X�y�C���̍�ȉƂ��Љ���Ƃ��C�M�^�[�Ȃ͎d���Ȃ��ɂ��Ă��C�s�A�m�Ȃ̎��v�����|�I�ɑ����̂͂Ȃ��Ȃ̂��B�Ђ���Ƃ��Ă��̏��Ȃ́C�Ŋy��̓����������C���Ŕ��t�����˂�s�A�m���C�Ƒt�̏ꍇ������ŋ��Ղȃ��Y�����J��o�����Ƃ��ł��邩��ł���C���ꂪ������̊��҂���X�e���I�^�C�v�ȁu�X�y�C����v���ł��e�Ղ����邩��ł͂Ȃ����ȂǂƎv�킸�ɂ͒����Ȃ��̂��C���̃��@�C�I�����ȑI�ł��B�����イ�����܂�ł���킯�ɂ������Ȃ������������t�ł邩��ł��傤���B�Ƃ���ǂ���ɃW�v�V�[�L���߉��������܂�C���[�_���Ȏ�����ƁC���X�L�����𑝂����t�ɍʂ��Y���邢���ۂ��C���ꌩ�悪���ȃt�������R�E���Y���͊ŁC�����قǂɉ����ȃ��}���h���y�ƂȂ��Ă���B��┖���Ȃ���ȑz�͂Ȃ��Ȃ��ɖ��͓I�B�h�r���b�V�[�O��̕����}���h���C���j���I�ɂ����悤�ȃC���[�W�������Ē����C�O��邱�Ƃ͂����Ȃ���Ȃ��ł��傤���B�\���X�g�̃��o�[�c�����1963�N�m�[�U���v�V���[�B�o�g�̃C�M���X�l�B�������y�@���o���̂��C�t���u���C�g�̏����ăA�����J�ւ����w���������ŁC�T�~���G���E�A�V���P�i�[�W��W�F�[���E���b�`�ɂ��w���������Ƃ�����Ƃ��B���ۓI�Ȏ�ܗ��͌�������Ȃ����̂́C1973�N���烍���h���ɋ��_���ڂ��Ċ����Ȃ����Ă���炵�����{���j�Ƃ��ǂ��r�͗ǂ��C�K�x�ȗ͊��Ɗm���ȃs�b�`�C����̂���ׂ߂̉��F�͌����ł��B���ꂾ���ɁC���Ɏc���̑����^������₨�e���ŁC�[�����t�̗ǂ���\��������Ă��Ȃ��͎̂c�O�ł��˂��B�������� |
 Hans Krása "Quartetto / Tanz / Three Songs / Thema mit Variationen"
(Channel Classics : CCS 3792) Hans Krása "Quartetto / Tanz / Three Songs / Thema mit Variationen"
(Channel Classics : CCS 3792)La Roche Quartet : Marat Dickermann, Sarah Paynes (vln) Jan Kokich (vla) Rudolph Grimm (vc) 1899�N�v���n�ɐ��܂ꂽ��ȉƂ́C������e���W�����e���g�̈�l�B�ٌ�m�̕��̂��ƁC�v���n�̃h�C�c���y�A�J�f�~�[�i�݁C���ƌ�v���n�����̌���̐��y�w���E�ɏA���܂����B�ʉe�͂��܂�Ȃ����̂́C���̓����C���̌���̉��y�ē������c�F�������X�L�[���瑽��ȉe�������̂��Ƃ��B�ނ�1927�N�Ƀx�������֖߂����ۂ͂��̌��ǂ��C�����Ń��[�Z���Ƃ��琂��Ďw�������̂������ł��B1938�N�ɂ͎��������̉̌��w�u�����W�o���x�Ŋ��ɑ傫�Ȑ�������ɂ͂��Ă������̂́C1942�N8��10���Ƀi�`�X�ɂ���ĕ߂炦��ꑗ�v���ꂽ��̃e���W���������e���ŁC��ȉƂƂ��Ă̍ł��P���������X���}���邱�ƂɂȂ����͔̂���ł����B�{�Ղ͂��̓����Ɏc���ꂽ�S�҂̎����y��i�^�B�h�C�c�C�j���[�W�[�����h�C���V�A�C�p���ƁC�����o�[�̒N��l�o�������Ȃ�1988�N���c�̃����[�`�F�l�d�t�c�̉��t�Œ����܂��B��t�悩�炶�킶��Ƒ��荞�܂��s����忓��ƁC�ŋC���܂R�~�J���Ȏ�������C����f���ڋ��ɗ��݂������܂́C�����ɂ��e���W�����e���g�B�������C���̍�ȉƂɔ�ׁC�ǂ����������R�~�J���ȓŋC�͏��Ȃ��C�Z�l�g�ɂ�����f�����I�Ȓn�����ƌ������Ɏx�z����Ă���B���������[�����߁C�d�����I�݂Ɏg���āC�O�d�t�Ƃ͎v���ʂقǍʂ�L���ȋ������w���ȁx��C��M�ƂȂ����w���ƕϑt�x�̃h�C�c�E���}���h�I�ȓc����́C���p���y����ł��邱�Ƃ��낤���Y�ꂻ���ɂȂ�قǁB�~���ނ���悤�ȕs���a���̃A�C���j�[���T���߂ŁC���̕ӂ肪���܂ЂƂe���W���g�̒��ł��]�����ς��Ƃ��Ȃ����R�Ȃ̂����m��܂���B�������C�l�I�ɂ̓e���W���g�ł͈�ԍD�������m��Ȃ��B�����Đ�������Ă���Ƃ͂����Ȃ����t���C�e�l�ǂ��������Ă܂Ƃ߂����Ă���Ǝv���܂��B�������� |
| Other Discs |
 Claus Ogermann "Piano Concerto / Concerto for Orchestra" (Decca
: UCCL-1024) Claus Ogermann "Piano Concerto / Concerto for Orchestra" (Decca
: UCCL-1024)Claus Ogermann (cond, p) National Philharmonic Orchestra �W���r���̑�\��w�g�x�́C�������ŗJ���Ɉ�ꂽ�nj��y���ɂ���Ė�����s���̂��̂ɂ������A�����W���[�C�I�K�[�}���B�V���n��͍����Ă����u���b�J�[�ɁC�~�X�e���A�X�ȃx�[����Z�킹�Ă������͔̂ނł������C�ŋ߂̓_�C�A�i�E�N���[���ɂ��I�P�����[�ĂĂ����Ă��܂����B���Ȃ薼�𐋂���1980�N��ȍ~����́C���X�ɃN���V�b�N���ւƔ�d���ڂ��Ă���悤�ŁC�{�Ղ͔ނ��{�i�I�ɃN���V�b�N�֎��g���ʂ�����B1991�N��̊nj��y�̂��߂̋��t�ȂƁC1993�N��̃s�A�R���^���Ă��܂��B�k���W���Y���̂������ő@�ׂȏ�C�J���������Ղ�܂݂����ɖ�a���́C�W���Y�N���̔ނ̎��������ǂ��Ӗ��Ő�������Ă���C�ϋɓI�Ȕ��_�Ƃ��ĕ]���ł���B���̔��ʁC����͔ނɌ��炸�W���Y����N���V�b�N�֗����l�Ԃ̂قƂ�ǂ������Ȃ�ł����C�ނ��܂��̈ʖ@�I�ȍ\���͂�����肵�Ă��܂��܂��B��������ނ̕ҋȍ�i���Ă��C�ǂ�����̒����a���������������ۂ��C���܂葽���I�ȓ����͂���܂���ł����B�W���Y�Ȃ炻��ł��l�ɂȂ�ł��傤���C�N���V�b�N�͂����͂����܂���B�啔�ƕ������C���̘a�����������Ă��܂��C���܂��ɏ㕨���������ʁC�����i���t����Y���j�̕ω����R��������ŁC��낪�d������ł��܂��܂��B�ꌾ�ł����C�_���Ղ��A�}���ۂ��B�Z���X�͌����Ĉ����Ȃ������ɁC�r������Ƒւ��������̂̌��E������悤�ŁC�u�C�~�y�ł��˂��B���Ȃ݂ɖ{�Ղ̃I�P�́u�i�V���i���E�t�B���n�[���j�b�N�v�ǂƂ��������ł��B�m���Ȃ��C�ǂ��̃i�V���i���ł����ˁB����Ƃ������t�B�����Ă��Ƃł����H���C���t�͗ǂ��ł��B�s�A�m�������A�łŎ�A�b�v�A�b�v������̂́C���Z�ʂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������� |
 "Violin Sonata in G Major (Lekeu) Violin Sonata in G Minor (Debussy)"
(Philips : UCCP-3498) "Violin Sonata in G Major (Lekeu) Violin Sonata in G Minor (Debussy)"
(Philips : UCCP-3498)Lola Bobesco (vln) Jacques Genty (p) �s�J�C�`�ɕi������O�����~�I�[�����f���炵���Ƃ���v���Ă����t�����N�̃\�i�^�ŁC�Ƃ���l���u���ꂼ�ō��v�ƑE�߂Ă����̂����̏����C�悲��2003�N�Ƀx���M�[�Ő������������[���E�{�x�X�R����ł��B1921�N�N���I���@���܂�̃��[�}�j�A�l�ł����C�o�g�Z�̓p�����y�@�B1934�N�Ɉꓙ�đ��Ƃ��C1937�N�̃C�U�C���ۂŗD�����Đ��E�I�ɒm����悤�ɂȂ�܂����B�C�U�C�ɐS�����Ă��C��N�̓x���M�[�ɋ��_���ڂ����悤�ŁC���������������y�c��1958�N�ɑn�݂����̂��C���̐l�����������ł��B�{�Ղ͂���Ȕޏ����C�Ȃ���1981�N�ɍ�ʌ��̐V���s����قŘ^���������N�[�ƃh�r���b�V�[�̃\�i�^�W�B�ǂ�قǏ�肢�̂��C�ɂȂ�C�����Ɍ㉟������Ă̍w���ƂȂ�܂����B������������̓C�U�C���ۂ̔e�ҁB���F�ɂ͌���Ɨ͊�������C�}�g�L���B�t�����R���x���M�[�y�d�炵�������C�̂��鉉�t�B���j�I���ՂƎ����グ���C�Ĕ����ꂽ�̂���ʁC�[���s���ɂ͍s���̂��m���ł��B�������C�������ӂ���ƁC���m�Ȃ悤�ł��Ĕ����ɂ����s�b�`�C�r�u���[�g���ӂ���ɕς���ؗ͂̒ቺ�C����͂�����̂́C�ۉ�̋P���ɏd�������݂̏o�����F�E�E�����ĉ����C�ׂ����A�N�Z���g�z�u��Y�����߂ɁC�V�l���L�̋Z�p�I�A������߂̖�������������Ă��܂��B���ɁC�Ȃ����Y�킳���ς�d�C�̎������C�����k�̂悤�ȃh�r���b�V�[�͈������̈��B�ʂ̈Ӗ��ŋ����鉉�t�Ƃ����܂��傤�B�̂͊m���ɑ�����肩�����̂ł́B�������C�^����������60�˂ł�����E�E�B�������琸�͓I�ɘ^�����������Ă�����C���邢�͕]�����ς�����ł��傤�ɁB���N�g���C�͂Ɠ��̂̐�����I��ɂ��Ă��܂����c���^���B���肶��Ȃ����̂́C�s�A�m����۔��B�債�����Ⴀ��܂���B������ |
![]()
| Recommends |
 "Jazz in Britain '68-'69" (Vocalion : CDSML 8418) "Jazz in Britain '68-'69" (Vocalion : CDSML 8418)�@bouquet garni �Ashepherd oak �BBessie �Ccircles on ice �Dwinter song John Surman (bs) Alan Skidmore (ts) Mike Osborne (as) Harry Beckett, Kenny Wheeler (flh) John Taylor (ep, p) Harry Miller (bg, eb) Tony Oxley, Alan Jackson (ds) �ߔN�C�������i�މp���W���Y�B���̍��̃W���Y�E�̖ʔ����́C���Ƃ����Ă��v���O���b�V���E���b�N�{�Ɩ{���Ȃ��Ƃł��傤�B���݂ł��������̃W���Y�����̑������C�Ⴉ�肵���Ɉꖇ����ł������Ƃ�����C���b�N�E�̍ːl�ƃW���Y�E�̍ːl���Ք��荇�����Ă���1960�N�ォ��1970�N��O���ɂ����Ẳp���W���Y�ɂ́C�T�N�����œ��B�����ފ݂̐V�嗬�h���[�u�����g�̎ێq��K�ł͌v��Ȃ��ʔ���������܂����B�{�Ղ́C1960�N�㖖�̉p���W���Y�E�V�[�������[�h���Ă����Q�̃O���[�v�̃Z�b�V�������W���������ՁB�O���O�Ȃ́C1944�N�^�r�X�g�b�N���܂�̃W�����E�T�[�}�������郆�j�b�g�̘^���ŁC�@�ł͎O�ǂ݂̂ɂ��W���I�����C�A�ł͂T�ǂɒʓd�n�g���I���������J���^�x���[�F�Y���V�嗬�h�W���Y�B�����ۂ��C�C�D��1942�N�����h�����܂�̃A�����E�X�L�h���A��������d�t�c�̉��t�ŁC���I�[�\�h�b�N�X�ȉp�����̐V�嗬�h�W���Y�������܂��B�\�����Ƃ�C�O�����T�[�}���C�㔼���X�L�h���A�����[�h����B�𒆊Ԃɋ��\����������炩�ȂƂ���C�P�Ȃ�Z�b�V�����̊W�߂ł͂Ȃ��C�ǎғ��[�̃|�[���E�E�B�i�[�������ނ�ɂ��j�V�����C������Ƃ����邱�Ƃ��ŏ�����Ӑ}�����C���삾�����̂ł��傤�B�t���[�����Ȃ��T�[�}���ł����C�{�Ղł���炵���͇̂@���炢�B�S�̂ɃJ���^�x���[�ƐV�嗬�h�H���Œʂ��Ă���C�����̂ɂ��肪���ȎU�������w�ǂȂ��Ɉ��S���Ē����܂��B���̊�G�ꂩ��\���b�h�ȃ��[�h�E�W���Y������������ɂ́C���Ȃ����L���Ē������Ȃ��ł��傤���B���������� |
 Joel Weiskopf "Devoted to You" (Criss Cross : Criss 1293 CD) Joel Weiskopf "Devoted to You" (Criss Cross : Criss 1293 CD)�@beauty for ashes �Adevoted to you �Bgiving thanks �CNovember �DSt.Denio �Ethe strongest love �Fyou must believe in spring �Gwondrous love �Ha mighty fortress �Ione bright morning Joel Weiskopf (p) John Pattitucci (b) Eric Harland (ds) �C���t�������N���X�E�N���X����̃��[�_�[����S���ɂȂ�W���G������B�u�E�H���g�E���C�X�R�t�́E�E�v�]�X�̖����͂����v��܂��B�����d�߂̃��Y��������J��o�����i�C�[���Œ[���ȑŌ��ƁC���ǂ��P��ꂽ�]�����S���������f�B�A�X�ȍ�ҋȗ͂́C���̐l�Ȃ�ł͂̎������B���ꂪ���܂����Z��ʼn��t�������p������傫�ȏ��Ȃɂ��Ȃ��Ă���܂��傤�B2007�N���\�̖{�Ղ́C�W�����E�p�e�B�g�D�b�`�Ƀu���C�A���E�u���C�h�����ޒ����ȃ��Y�������o�b�N�ɂ����O��ɑ������́B�����肫���Ă̘r��������ɂȂ����G���b�N�E�n�[�����h�ۂɉ����C���Y���͂����������C���ǂ��������܂�܂����B���������C���̓��܂߁C�ނ̑��ۂ̐l�I�͈�x����邱�Ƃ�����܂���ł����˂��B�Ђ���Ƃ���ƁC���̐l�̍�i���̒��j�ɂ͑��ۂ�����C���̂����ɏ㕨����ׂ�`�ʼn��y�����l�Ȃ̂����m��܂���B����Ȏא����܂�ł��Ȃ��Ǝv�킹��{�ՁC���e�����̃g���b�N�������܂����B��{�H���ɂ͕ω������C�d�グ���ՐB�y�X�Ƃ��̕ӂ̃g���I�Ղ��Ă�����̗ǂ��ŐM���͗��炸�C�l�I���܂ߐS�z�v�f�͖w�ǂ���܂���B�B��C�ɂȂ�_������Ƃ���C���̃��e���ւ̊�ȌX�|�B���e�����͂ǂ����Ă��C�S�����ɔ�ׂ�ƃ��Y�����d����ۓI�ɂȂ�܂�����C�����ȂƂ���C����t�������ɂȂ��Ă��܂��B���̂��߂��C���ɂ������đ��ۂ��O�ɏo�āC��l�����������Ė��ɉ�������͐@���܂���B�Z�I�h�ł͂Ȃ��Ԃ�C���ۂɑ傫�����|�������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���C�������艉�t�̏��������ڗ����ʂɂȂ����ܑ͖̂̂Ȃ������ł����˂��B���������� |
 Rahsaan Roland Kirk "I, Eye, Aye: Live at the Montreux Jazz Festival"
(Rhino : R2 72453) Rahsaan Roland Kirk "I, Eye, Aye: Live at the Montreux Jazz Festival"
(Rhino : R2 72453)�@Rahsaantalk 1 �Aseasons �BRahsaantalk 2 �Cbalm in gilead �Dvolunteered slavery �ERahsaantalk 3 �Fblue rol No.2 �Gsolo piece �Hserenade to a cuckoo �Ipedal up Rahsaan Roland Kirk (reeds, winds) Ron Burton (p) Henry Pearson (b) Robert Shy (ds) Joe Texidor (perc) ���ɐ��{�̃��[�h�y������������e�Œm��l���m�郍�[�����h�E�J�[�N�́C1936�N�R�����o�X�o�g�B�암�̃u���[�X��\�E���E�W���Y�C�S�X�y���̓y�L���t�B�[�����O�ʂɂ������C�����Ȃ��l�������������f�B�A�X�B���ɏ���Ă͚X�萺��グ�C�@�ɓJ��˂�����Ő�������C���[�h�������Ĉ�l�Έʖ@���������B���̋���ȃL�����䂦�ɁC�T�C�h�����Ƃ��Ă͐�����قǂ����������݂����܂���ł������C1956�N�̏����[�_�[��\��C���[�_�[�Ƃ��Ă͏��Ȃ��炸���̘^�����c���܂����B�{�Ղ�1972�N�Ƀ����g���[�E�W���Y�Ղ֏o�������ۂ̎����^���B�킸���R�N��ɔ��g�s���ƂȂ�C�T�N��ɐ�������Ƃ͎v���Ȃ��قNjC�����悭��NJy��̐��X�������F�ƁC�قǂ���G�l���M�[�̕������Ӗڂ��܂��B���C�u�Ƃ������Ƃ���`���C���ԉ��т������t������ق�B���̃��[�J���ȑ哹�|�l���v�킹��ނ̌|���̖����́C�ނ���f���Ō���ق������������͂߂�悤�ȋC������̂��m���B�E�\���Ǝv������{�Ղ��꒮�����̂��C�f���t�����Ē�����Ɨǂ��ł��傤�B�S�̕����܂ܕ@�J�𐁂��C���C�ɋq�ȂV����ނ��C���������������b������͂̃T�C�h�����ƁC�g�����蔏�q�Ō}����q�ȁB�����ޔ��܂�����C��Ǒ̌����Ȃ���C�l�ɂ���Ă͓����������ւƃC�b�Ă��܂�ꂽ���y�o�J�̃��N�K�L���݂ĕ������Ă��܂����Ƃł��傤�B�ڂ��_�ɂȂ��Ă��܂����M���͂��ЇH�C�I���B���̋C�ɂȂ�ΐ^�����ȃW���Y�������l�E�E�Ƃ����̂́C������Έ�ڗđR�B�������̌��_�́C���̇I�̖��_�o�ȃt�F�[�h�E�A�E�g�ƁCCD�̌��E��������Ƃ����Ӗ��ł��B���������� |
 Giuseppe Bassi Quintet "We'll be Together Again" (YVP : CD 3100) Giuseppe Bassi Quintet "We'll be Together Again" (YVP : CD 3100)�@l'angelo che vola più in alto �Alove walked in �Bwe'll be together again �Chaze �Dparla più piano �ERoma nun fà la studida stassera �Fmemory of a dream �Gbass tune �Hgood morning heartache �Ijehu Giuseppe Bassi (b) Dado Moroni (p) Daniele Scannapieco (ts) Lorenzo Tucci (ds) Fabrizio Bosso (tp, flh) Guido Di Leone (g) ���[�_�[��1971�N�o�[���̏o�g�B�����̐�y���x���g�E�I�b�^���B�A�[�m�Ɍ��o����C�ނƂƂ���1994�N�A�p�g���A�E�N�C���e�b�g�������B1997�N�ɂ̓X�P�}�E�N�C���e�b�g�ւ̎Q���ɂ���Ĉɂ̕ێ�h�W���Y���D�ލD���Ƃ̊ԂŘb����ĂсC���̌���t�@�u���c�B�I�E�{�b�\�C�G�}�j���G���E�`�[�W�[�獡�l�n�[�h�o�b�v�̍D���ȖʁX�̘e���ł߂Ă�����͎҂ł��B�{�Ղ͂���Ȕނ��C2002�N�ɔ��\���������[�_�[��B�T�C�h��������ɘe���ł߂Ē��ǂ��Ȃ����t�@�u���c�B�I�E�{�b�\�ȉ��C�X�P�}�E���R�[�h�オ��̖ʁX�����ɏ������Ă��܂��B�C�^���A�̃W���Y���������ɂȂ���́C��G������������ʼn����������Ă���ł��傤����C�ő��]�v�ȉ��͗v��Ȃ��悤�Ȃ���ł����C���ۉ~�Ղ�炷�ƁC����ȏ�Ȃ��قǗ\�蒲�a�I�ȕێ�h�n�[�h�E�o�b�v�B�r�����������Ă��邤���C�ςɘM��Ȃ���ҋȂ��D�܂����B�ނ͂��̌�ɂ�2004�N�Ɂw�}�C�E�������A�C�x�\���邱�ƂɂȂ�܂�����ǁC�啨��������������̂ق����o���͈ꃉ���N��ł��傤�B�w�ǖڗ����Ȃ��M�^�[�Ɏ֑����͕Y�����C�}�����̇@�ɂ�����Ȃ��t�@�u���c�B�I�E�{�b�\�̃��b�p�͑��ς�炸�f���炵���B�҂ł����C�ǂ��ƂȂ��o�b�v�ł̃}���O�����[�E�~���[�݂����ȘV�Ԃ���Y�킹���_�h�E�����[�j�̃s�A�m���o�����X�ǍD�B�������t���ȂƂ���̂���e�i�[���앐�m�I�ȃ\�E���t���l�X�������C�{�ՂɌ����Ă͍D���t�B�ϐ��̎�ꂽ�D���e��ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���������� |
 Jimmy Greene Quartet "Forever" (Criss Cross : Criss 1245 CD) Jimmy Greene Quartet "Forever" (Criss Cross : Criss 1245 CD)�@old rugged cross �Ain many tongues �Bcome sunday �Cforever �DNMG �Eyou make me feel brand new �Fpower �Ghe is lord Jimmy Greene (ts, ss) Xavier Davis (p) John Benitez (b) Jeff 'Tain' Watts (ds) �ڕӂ�܂ł́C�܂��[���y����R���g���[���ł����C�������y�ȂƃA�����W�����g���݂̐F���Z�������W�~�[�E�O���[���B���܂�C�ɗ��߂����Ƃ͂Ȃ������̂ł����C���ꂩ��͂��P�`�Q�N�قǂ̊ԂɁC�݂�݂�r���ǂ��Ȃ�C�e���ŎQ�����Ă���A���o���Ŕނ����Ă���ƁC���炭�̓A�C�h���ɂ��ċ���ł��낤�W���[�w����̓����I�Ȗǂ��C�}���ɉ���Ă���悤�����`����Ă��܂����B�u�I�I�b�����m��C���ɏ�肭�Ȃ��Ă�I�ǂ����Ō���������E���Ă݂邩�E�E�v�����v���Ă����Ƃ���ցC�ܗǂ��苖�ɗ����Ă����̂��C2003�N���\�̖{�ՁB������̑��삩��R�N�U��̃��[�_�[��O��ŁC���X�L�����A���̃����E�z�[���E�J���e�b�g�B�����ċ����������Ă͂��Ȃ����������C������Ƃ��ꂾ�������炳�܂ɐi�����郄�c�͋L���ɂȂ����Ǝv�������炢�ł�����C���炭�{�l�͈�ԗǂ������̐������������Ă�����ł��傤�B�����f�B�b�N�ȃ��[�h�E�s�A�m��e���C���̎�̔��t�ɂ͍œK�C�ł��낤�U���B�A�[�E�f�C���B�X���e�ɉ��C���ʂ̃��Y�����������łߐw�e�����S�B�O��͂Ȃ����낤�E�E�Ƃ̓ǂ݂͂U�����͐����ł����B���t�Ɋւ��Ă͒����̐i���𐋂��Ă���C�[������Ƃ��ĊŔ�Ă��܂��B�����c�O�Ȃ̂́C���܂Ƃ܂�������A�����W�ƍ�ȁB�X�^���_�[�h�͂��P�肷���C�o�b�v�ƃ��[�h�̊Ԃł�⒈�Ԃ���ɂȂ����悤�ȃI���W�i���̈ӏ����C�ɂ����Ƃ����ΐɂ����ł����˂��B�ł��C�����e�i�[�}��������܂ł̃C���^�[�o���ɂǂꂾ���剻�����邩���C���̐l���炢�I���ɏؖ�������́C�����ŋߋL���ɂ���܂���B�O��������Ă�����Ȃ�C����ׂ邾���ł��[���ɖ����߂邩�Ǝv���܂��B�������� |
 Brian Lynch "In Process" (Ken Music : 011) Brian Lynch "In Process" (Ken Music : 011)�@four flights up �Aflamingo �Bin process �Cdo what make you mad �Dafter dark �Ethe new arrival �FI should care �Gso in love �Hbirdflight Brian Lynch (tp) Javon Jackson (ts) Benny Green (p) Dennis Irwin (b) Anthony Reedus (ds) 1956�N�C���m�C�B�E���o�i�o�g�C�C���t����50��ƁC���͂�x�e�����̈�ɍ����|�����Ă���u���C�A���E�����`�B�ނ���{�ňꑫ�����L���ɂ����̂͏H�g�q�q�̃W���Y�I�P�ł������C���͂��̑O����`���[���X�E�}�N�t�@�[�\���ƃz���X�E�V�����@�[�̃R���{�ɍݐЁB���l�Ȃ��獜�̐��܂Ńr�E�o�b�p�[�Ȃ��̎p���́C������₷���čD�������Ă܂��B�{�Ղ͓��{�l����X�^�b�t�̂��ƁC�u���C�L�[�Ǔ��ՂƂ���1990�N�ɐ������܂ꂽ�C�R���ڂ̃��[�_�[��B�������ɘR�ꂸ�C�ێ璆���n�̓`���h�n�[�h�o�b�v�E�`���[���������Ɣz�V����Ă��܂��B���ɘV�Ԃł��炠��}���O�����[�C�x�j�[�E�S���\�����̒��s���W�����H���E�W���N�\����C�����̓��{�l�X�^�b�t�̍D�݂����̂܂�܁B�`���h���̊�G��ƂȂ�C�o�Ă��鉹�͒������Ƃ��\�z�\�ł��傤�B���̃A���o���̔��_�̓\���]�X�����C�A���o���Ƃ��Ă̂܂Ƃ܂�̗ǂ��B�y�Ȃ�A�����W�����g���ǂ���ǂ������Ă���C�ӏ������J�B�ŋ߂܂ŏo�����Ă���ނ̐����A���o���ƕ��ׂĂ��C���炭�����ɏ�ʃN���X�Ȃ̂ł́B�\���ɂ��Ă��C���ꂾ���̖ʁX�B�����l�܂�Ȃ����̏o�悤�͂����Ȃ��C�e�l�Ƃ��y��_�̏o���Ŏ茘�����t���܂Ƃ߂܂��B���ЂƂ̂�����Ȃ��\���X�g�����̒��ł́C�W���E�X�i�C�f���̏o������������Ă��܂��傤���B�X�i�C�f���̃A���o���Ŋ��S�����L�����ĂȂ���ł����ǁC�����ł͎����O�̃L���m���{�[���D�����I�݂ɐ������Ȃ���C�����f�B�b�N�ȃt���[�Y�ւƂ܂Ƃ߂����邱�Ƃɐ����B�D����������ł��傤�˂��B�������� |
 Peabo Bryson / Roberta Flack "Born to Love" (EMI : CP28-1054) Peabo Bryson / Roberta Flack "Born to Love" (EMI : CP28-1054)�@tonight, I celebrate my love �Ablame it on me �Bheaven above love �Cborn to love �Dmaybe �EI just came here to dance �Fcomin' alive �Gyou're looking like a love to me �Hcan we find love again Peabo Bryson, Roberta Flack (vo) Marcus Miller (syn, b) Greg Phillinganes, George Wadenius, Richard Horton, Dann Huff, Paul Jackson, Jr., Tim May (g) Richard Tee, Mark Parrish, Paul Delph, Vance Tayler, Robbie Buchanan, Michael Boddicker, Randy Kerber (p, rhodes, syn, key) Carlos Vega, Buddy Williams, Jim Keltner, John Gilston, Andre Robinson (ds) Anthony MacDonald (perc) Leland Sklar, Nathan East, Abe Laboriel (b) Jai Winding, Jerry Corbetta (arr, rhodes, key) Felipe Mantine (fl) Gene Page (arr) Bobbye Hall, Charles Bryson, Paulinho Da Costa (perc) Bob Gaudio (syn, arr, rhodes, p, ds) Thaddeus Johnson, Dan Dillard (tp, flh) Pete Christlieb, Ron Dover (sax) etc. �\���ł͋��炭�u�D�����̂��āv�ł̂ݔF�m����Ă��郍�o�[�^�E�t���b�N�́C1969�N�̃f�r���[��C�_�j�[�E�n�U�E�F�C�Ƒg��Ńq�b�g��A���B�������C1979�N�ɔނ���э~�莩�E���Ă��܂��܂��B���ӂ̔ޏ����C�㊘�Ƃ��Ĕ��H�̖�𗧂Ă��̂́C1976�N�Ƀf�r���[��������̐V�l�s�[�{�E�u���C�\���ł����B�{�Ղ͂��̍ŏ��̐��ʂŁC�N���C�G�b�g�E�X�g�[���̂͂���Ƃ������邨�̇@�ł̂ݔF�m����Ă���q�b�g��B�u���O�͒m��Ȃ����NjȂ͒m���Ă�v�̑㖼���Ƃ�������@�ł����C���͖{���ł͂��������r���{�[�h��16�ʂɂȂ������x�B�A���o����25�ʂǂ܂���Ă������ł����H���{�Ńo�J���ꂵ�����R�́C��ɂ���ɂ��u���W�X�g���̃^�C���Ɓg�^�C���b�v�h��������ɑ��Ȃ�܂���B���̎�́g���ꂽ���ȁh���������A���o���́C�q�̂P�ȈȊO�͏o���炵�̃p�^�[�����唼�ł��āB�̐S�̇@�̑�Â��������D�݂ɍ��킸�C����܂Ŗ{�Ղ�^�ʖڂɒ������Ǝv�������Ƃ͂������܂���ł����B����ς͂����܂���B���܂���250�~�ŏE�����̂��@�ɍ���C�^�ʖڂɒ����Ă݂܂��ƈӊO��ӊO�C�J�b�g����Ȃ��������̊y�Ȃ��Ȃ��Ȃ������낢�B�킯�Ă��o�J���b�N�v�Ȃ̏������A�̔������͂������B�V���O���Ȃɕ����Ȃ��قǗǂ������Ă���B���t���r�����̃X�^�W�I�E�l�������Ă̎�ł��B���ƂȂ��Ă͏����T�����A�����W������܂�����ǁC���������s�����\�t�g�E���b�N��N���C�G�b�g�E�X�g�[���̖��ՌQ�Ƃ��[����ׂ�����e�Ǝv���܂��B����C�������ꂵ�܂����B�������� |
 Jean-Pierre Como "Storia..." (Naïve : Y226136 AD 098) Jean-Pierre Como "Storia..." (Naïve : Y226136 AD 098)�@primavera �Ale plus beau tango du monde �Blungo mare �Cestate �Dgianno di festa �FLéa �Gallegria �HSyracuse �Ivalse du premia jour �Jstoria... �Kpost scriptum Jean-Pierre Como (p) Thomas Bramerie (b) André Cecarelli (ds) �e���Ƃ��Ă͂Ƃ���������Ƃ��Ă͏����̃��[�_�[�́C1963�N�p�����܂�B���@���̒ʂ�C�^���A�n�ږ��ł��B�x���i�[���E���[���[�C�~�V�F���E�T���_�r�[�C�t�����\���E�N�`�����G�̂���q����ł����C��w����܂ł͉��y�@�Ő��K�ɃN���V�b�N�������Ă��������ł��B1983�N�̃f�t�@���X���ۂ𐧂����M�^�[�̃��C�E�E�B���u�[���C�T�b�N�X�̃A�����E�h�r�I�[�T���1984�N�Ɂy�V�N�X���z�Ȃ�t���[�W�����E�o���h�������B���̌�̊����͂قƂ�ǂ����̃o���h�ƁC����̃��[�_�[��̗��ւœW�J����Ă���悤�ł��B�T���ڂɂ�����{�Ղ́C���A���h���E�`�F�J���������ۂɍ��鍋�ȕҐ��ŁC2001�N�ɔ��\����܂����B�t�����X���܂�̃C�^���A�n�Ƃ̏o��������ǂ݂悤�ɂ���Ă͓ǂ߂����ȉ��́C�Â�����ƁC�ȑf�Șa���C�����Ȃ���ۂ��Ō����������C�C�^���[�E���}���h�̏����Ȓ����B�t�@�E�X�g�E�t�F���C�I��������̃��x���g�E�V�y���ɒʂ����c�X�Ƃ����s�A�j�Y���ƍ�ҋȗ��V�̎�����ł��B�Ⴂ������Ƃ���C�t���[�W���������ږ��̎q�炵���C�S�����Y���ւ̎������ŁC��i���̔��w�ɂ����ăt�����V�X�E���b�N�E�b�h��Ɉꖬ�ʂ�����̂������Ă��邱�ƁB�W���P�b�g�ɍڂ���ꂽ�Z�s�A�F�̂��ʐ^�́C�@����Ƃ���C�ʔՂŃg���r���[�g���邱�ƂɂȂ鈤���Ɨc�����̎����ł��傤���B���ꗬ��ăp���֒H�蒅�����Y���̋L�����C�ǂ��ƂȂ��W�v�V�[�̏L����Y�킹��^�w���^��A�����W�����g�̂䂦��Ȃ̂ł��傤�B���������C�ނ����ӂɂ��Ă���E�B���u�[������̓t�������R�E�M�^�[�̖���ŁC�W�v�V�[�E�L���O�X�̊W�҂������ł���ˁH�������� |
 A.Pasqua, D.Carpenter, P.Erskine "Standards" (Fuzzy : PEPCD014) A.Pasqua, D.Carpenter, P.Erskine "Standards" (Fuzzy : PEPCD014)�@the way you look tonight �Adear old Stockholm �Bdeep in a dream �Ccon alma �Dit never entered my mind �Espeak low �FI'm glad there is you �GI hear a rhapsody �HI'm ld fashioned �II could have danced all night Alan Pasqua (p) Dave Carpenter (b) Peter Erskine (ds) �Z���X���ǂ����͈ӌ��̕������Ƃ���ł��낤�Ƃ͂����C���Ȃ��Ƃ����̃g���I�̉����\����Ƃ͎v���Ȃ��\���̖{�Ղ́C�������薨����ԂɂȂ����A���v���W�F�N�g�̐V�^���B�����ɗ��ĉ����v�������C�X�^���_�[�h�Ȃ������ׂĈꖇ����Ă��܂����B�ǂ������{�Ղ��o�Ă���悤�ŁC������Ȃē��{�l����̂������ƒQ���Օ]���������܂������C���Ȃ��Ƃ��{�Ղ̃N���W�b�g�ɖM�l�̖��O�͂���܂���B���Ƃ��ƃz�[���Y���[�X�l���̃p�X�J�́C�A�[�X�L�����X���ǂ��Ȃ��R��I�ȋȏ����̍˂��L���B�m���ɖk����Y���D��F�̃A�����W�͊��S�������̂́C��������Ȃ��������炷�鋭���ȃ��n����Y���������ڗ��ҋȂ́C�S�̂ɂ��u�炵���Ȃ��v��ۂŁC�����ȂƂ��낱�̎O�l�ɗ]���ґf�ނ͎ז��Ȃ������E�E�Ǝv�킴��Ȃ������Ɣ��˂Ȃ�܂���B���{�l�ɃX�^���_�[�h�D���������͎̂��m�̎����ł����ǁC�܊p�}�C�y�[�X�ł�����i������Ă������t�Ƃ̉��ʂ��D���ł͂����Ă܂ŁC��������v����Ƃ�����C��͂���B������̔Օ]�����̈Ӗ��ł͂��Ȃ����I�O��Ƃ������܂���ł��傤�B�u�O��ӂ����сv�̊��҂𑁁X�Ɏ̂Ă�������Ƃ��ẮC�ނ���ٗl�ȂقǗǂ��^�ꂽ�W���ɔ��芅�сB�������Ǝv���������̑�u�`���ŁC��������{�̐^��ǃ}�C�N�ƂQ�g���b�N�̘^���@�݂̂��g�p�B�O�ꂵ�Č�����Nj������Ƃ̐G�ꍞ�݂Ɉ�킸�C�A�[�X�L���̃V���o�����̐��X�����ɂ͊̂�ׂ��܂����B�Q�{�����}�C�N���g��Ȃ������̈ʑ����c�܂Ȃ����Ƃ��C����قǎ��ɐS�n�ǂ��Ƃ́B���ʁC�Q�̑Ŋy��ɋ��܂ꂽ�J�[�y���^�[�̃x�[�X����������ł���̂͂����h���B���^��̔���Ȍ��E���I�悵�Ă��܂����E�E�Ƃ����Ƃ���ł��傤�B�������� |
 Ben Schachter "The Missing Beloved" (Ben-Jam Music : bjcd 334) Ben Schachter "The Missing Beloved" (Ben-Jam Music : bjcd 334)�@the missing beloved �Avisitation �Bsimultaneous �CI know you hate me* �Dbebrew* �Enext Ben Schachter (ts, as) Tim Hagens (tp) Jef Lee Johnson (g) Micah Jones (b) Erik Johnson (ds) Gary Bartz (as)* ���[�_�[��1962�N�y���V���o�j�A�B�m�[�X�E�E�F�[���Y�o�g�B���݂̓e���v����w�ŃW���Y�ȍu�t������T��C�t�B���f���t�B�A�����_�Ɋ������钆�����[�h�t�҂ł��B�f�C���E�z�����h��W�����E�]�[���C�W���}���f�B�[���E�^�N�}�C�T���E�����@�[�X�Ƃ̋������o�āC���吧��ՂȂ��琔���̃��[�_�[�Ղ\���Ă��܂��B�{�Ԃ�2002�N�ɏo�����̂ŁC1970�N��̍��l��s�W���Y�����̗�������ނǂ�ǂ�Ƃ�����p�����C�������M�^�[�̘a���Ƃ������肵�������ŁC�I�݂Ɍ���ւƏ��B�����͌Â��ǂ����l���y�ɒu���������ŁC�s�p�I�Ȑ����Ŗ��t�������Ă��������́C�Â��̓h���t�B�C�h���E�`�F���[�C�I�[�l�b�g�E�R�[���}���C�ŋ߂ł̓g�[�}�X�E�`�F�C�s����W�����E�]�[����̂���Ɉꖬ�ʂ��܂��i�����������[�_�[����̏����y�Ȃƃo�[�c���̉��F�́C�ǂ��ƂȂ��g�[�}�X�E�`�F�C�s���Ɏ��Ă܂��˂��j�B�E�l�E�l�ƔY�܂����̂�����Q�̃��t���C�����E�����f�[���ɂׂ�����u���[�X�̎���h��d�˂��悤�ȃW�F�t�E���[�E�W�����\���̃M�^�[�����x���B�����ē�ǂ��t�����g�ɐ����C���ݍ����̍����ۂ��s���a����ʂ��āC�����������ɕ�܂ꂽ�̓��̃e�B���p���A���C���I�݂ɕ`�o����B����������\�z�����ʂ�C�j�b�e�B���O�E�t�@�N�g���[�̏L�݂������Ղ�l�܂��Ă��܂��B������`�I�Œ������ɖR�����C����������Ȃ�I�ԊA�a�ȉ��ł͂���܂�����ǁC�Ȏґ����ŋZ�p�I�ɂ͑����Ƀn�C�E���x���B�암�a��̋C����W���Y�������łȂ���C���܂ɂ͂��������̂����������m��܂���B�������� |
  Jan Lundgren Trio "Landscapes" (Sittel : SITCD 9297) Jan Lundgren Trio "Landscapes" (Sittel : SITCD 9297)�@dalvisa �Aallt under himmelens fäste �Bblekinge �Cinbjudan till bohuslän �Dfjäriln vingad syns på haga �Ebrännvin är mitt enda gull �Fsmåland �Gslängpolska efter byss-kalle �Hglädjens blomster �Iden blomstertid nu kommer �Jmedley �Kjämtländsk kärleksmelodi Jan Lundgren (p) Mattias Svensson (b) Morten Lund (ds) �ނ̍ō����삪�w�X�E�F�f�B�b�V���E�X�^���_�[�Y�x�ł��邱�ƂɈ٘_�̂���l�́C�����͂��Ȃ��ł��傤�B���ۂ������̃A���b�N�X�E���[����X���X�E�V�F���x������C�f���}�[�N�̏r�˃����e���E�����h�֓���ւ�������2003�N�^���ՂŁC�猩�����Ƃ��Ă瑁���C���̍ō�����Ɠ��������n���w�W�𐧍삷��ނɂ��C�����Ƃ��̎��o�͂����ł��傤�B���ۂ̕ω��Ń��Y���͎���ǂ��^�C�g�ɂȂ�C���ʂ�◭�߂��r���B������̍ō�����ɔ�O�҂ٖ̋��ȑ�����������C�ǂ����������u���ʂɗǂ��g���I�v�ɂȂ�܂����B���Y�������ʂɂȂ����̂͊��F�̗��Ԃ����B�@�ɂ��Ƃ����Ε@�ɂ��B�^�C�g�ȏ��𑽂������������Y���̂������C��⋇�������Ȕނ̉^�w�Z�I�ɁC�����͂����Ȃ肪�����B�ꂷ��̂��m���ł��B�ނ�����͖}��ȃs�A�j�X�g����ꡂ��ɍ��������ł̘b�B�ۂ��[���ȃ^�b�`�͑��ς�炸�ŁC�E����ǂ��̂��C���^�������ėǂ��X�C���O����B�I�[�\�h�b�N�X�ȃo���b�h���C�M���̃�����Ŗ����߂�_�ł́C�[�����E�߂ł��郌�x���̓N���A���Ă���܂��傤�B����Ȗ{�Ղōł��C�ɓ���Ȃ����ƁB����́u���ō��X�H�v��CCCD�d�l�B���܂��Ƀp�\�q�ł��ǂ߂���x�̎ア�v���e�N�V�����B�p�\�q���g��Ȃ��l�͍ŏ�����R�s�[�Ȃ�Ă��܂��C�p�\�q���g���C���ӂ������ăt�@�C�����g�U����\�͂�����C�v���e�N�g�ȂNj���Ȃ��O���ł��傤�B���Ǒ�������̂́C��@�t�@�C���𗎂Ƃ����Ƃ��Ȃ��^�ʖڂɌ������C���b�s���O���������V��CCCD�̂܂ܒ����P�ǂȃG���h���[�U�[�����B���ݎ��̂����Ӗ��ł��B���ꂾ���^�b�`�ɐ_�o��z�郉���O����������ɓ��ӂ����Ƃ́B�Ԃ邤�������O�����̐S���ł������܂����Ƃ�B�������� |
 The Jazz Couriers "The First and Last Words" (Tempo-Jasmine :
JASCD 626) The Jazz Couriers "The First and Last Words" (Tempo-Jasmine :
JASCD 626)�@the theme: through the night roared the overland express �Aroyal ascot �Bon a misty night �Con a misty night (alt.take) �Dcheek to cheek �EMonk was here �Flast minute blues �Gif this isn't love �Heasy to love �Iwhisper not �Jautumn leaves �Ktoo close to comfort �Lyesterdays �Mlove walked in Tubby Hayes (ts, vib) Ronnie Scott (ts) Jimmy Deuchar (tp) Terry Shannon (p) Phil Bates, Kenny Napper (b) Bill Eyden, Phil Seamen (ds) ��������ɂ��Ă����y�t���~���S�z�Ƃ����W���Y�E�N���u�̂����痎�Ƃ����@�ɁC1957�N��4���Ɍ������ꂽ�W���Y�E�N�[���A�[�Y�́C1959�N8���ɉ��U�B�������Q�N�����������܂���ł�������ǁC�K�^�ɂ�����̗D�ꂽ�n�[�h�E�o�b�v����c���Ă����Ă���܂����B�ފ݂̃A�����Y�[�g���C�Y�[�g�̍I������ڗ����Ă����̂ɑ��C������̂Q�l�͘r�̂ق����o�����X���ǂ������C�K�x�Ƀ\�E���t���ō�������C���̂Ȃ��`�[���ł����˂��B�{�Ղ̓W���Y�E�N�[���A�[�Y���`�Ŏc�����ŏ��i1957�N8���j�ƍŌ�i1959�N7���j�̃Z�b�V�������J�b�v�����O�������́B�������O���̂T�Ȃ͒��������Ƃ���悤�ȋC�������ł����ǁC�ނ���ڋʂ͑o���̑����҂�����Ȍ㔼��B�C�ɂ��Ȃ����Ƃɂ��Ă��܂��܂��傤�B�������Y��O���t�B���Ȃǂ́C�\�E���t���ō��̂���e�i�[�}���֏d�x�ɔ�ꂽ����l�̃o�g���̓X�g���[�g�A�w�b�h�Ŏ��ɐ��X�����B���l�ł�����C�S�Ղ��e����p�����Ђ����Ă��C���̓����̃w�C�Y�̃��[�_�[�Ղ̒��ɂ́C�S�ՂƉߑ��C���̃A�����W�ŋ����߂�U�����̂����Ȃ��Ȃ��B��⓪�ł������ɂȂ肪���ȃw�C�Y������C�e�i�[�o�g���̎�œK�x�ɒg�߂Ă����Ƃ���ɁC���̃`�[���̊��ǂ������������Ȃ��ł��傤���B���Ȃ݂ɖ{�ՁC�V��H�[����LP�ŕ��������͗l�B��������z���āC��s���ł�CD�������œ������肳��Ă܂��B�����ɕΎ����I�S��̂Ȃ����͍����������������m��܂���B�������� |
 "The Benoit / Freeman Project" (GRP : GRD-9379) "The Benoit / Freeman Project" (GRP : GRD-9379)�@reunion �Awhen she believed in me �Bmediterranean nights �Cswept away �Dthe end of our season �Eafter love has gone �Fsmartypants �Git's the thought that counts �Hmirage �Ithat's all I could say David Benoit (p, key) Russ Freeman (g, synth, key) Nathan East, Abe Laboriel (b) John Robinson, Tony Morales, Mike Beard (ds) Steve Reid (perc) Kenny Loggins, Phil Perry (vo) Jerry Hey, Gary Grant (tp, flh) Dan Higgins (as) et al. �����W���P�b�g���G�O���āC���ÔՓX�ɕK�������Ă���y���b�s���g���Y�z�̃��[�_�[�C���X�E�t���[�}������ƁC�O���~�[�܂T����ւ�C�[�W�[�E���X�j���O�E�̑�\�i�f���B�b�h�E�x�m�����g��ŁC1994�N�ɔ��\�����R���{���[�V������B250�~�Ɩ��Ɉ����̂ł������Ă��܂��܂������C���̓x�m������͐����́C�G���@���X�ɕ������w�t��҂���сx���C�_�o�������ȍd���Ō����ǂ��ɂ����Ȃ������L��������܂��āB�ȗ��ނ̒��ÔՂɂ͈�x������o�������Ƃ��Ȃ��C�v�X�ɒ������ƂɂȂ�܂��B�M�^�[�ƃs�A�m�e����������������ɉ����C�x�m���͑S�҂ɓn���ăA�R�[�X�e�B�b�N�E�s�A�m�B�x�[�X�ɂ́C�ǂ����Ŗڂɂ����l�C�U���E�C�[�X�g�̖����B���ꂾ���؋��������Ă���C�v���W�F�N�g�����ɂ������āC�ꑫ�����r�b�O�l�[���̑�����ʂ��������y�t�H�[�v���C�z�̐������͂ƂȂ����Ƃ̎א����C���Ȃ����I�͂���ł͂���܂��܂��B10�N��ɂ͑��҂����܂����̂ŁC�����Ƃ��{�l�B�ɂ��C�����Ȃ炸�v��������c������i��������ł��傤�B�ȂɂԂ�x�m������ƃ{�u�E�W�F�[���X�ł͒e����Ƃ��Ă̊i�͔�ׂ悤������܂��C���b�s���g���Y�͑ł����ݕ�����Y���m���m���̃t���[�W�����B�i�������͔ۂ߂܂���B����ł��C���y�t�тŃA�R�M��O�ʂɏo���C�{�Ƃ����̂��̐��C�ݓI�G�L�]�`�Y���Ƒu�₩�ȏ���n�������B���n�߉��Ȃ����сC���̖ʁX������o���鉹���Ȃ��E�E�Ɩj�ɂ݂܂��B�l�I�ɂ̓P�j�[�E���M���X�̎Q�������A�������B�T���g���̃C���[�W�������ނ��C����AOR�F�Z�����Ŗ炵���ʍD�݂̍ːl�B�͂��P�Ȃ̎Q���Ŏ���Q�l���Y�킳���ς���ݍ��ށC�V���̋ȏ����\�͂Ɖ̏��͂ɂ͖ڂ��_�ɂȂ�܂����B�]�k���C���҂����E�̃J�o�[�͏X���B���Ƀi���V�X�Y���ۏo���̉̎�ɂ̓Q���i���̈��ł��B�������� |
 Laura Fygi "Introducing Laura Fygi" (Mercury : PG 900/510700-2) Laura Fygi "Introducing Laura Fygi" (Mercury : PG 900/510700-2)�@goodmorning heartache �AI've grown accustomed to her face �Blet's get away from here �Cwillow weep for me �Djust one of those things �Eimpossible �Fdream a little dream �Gmy foolish heart �Hgo away little boy �Idon't it make my brown eyes blue �Jguess who I saw today �Kgirl talk �Lout of sight, out of mind �Mstuck on you �Ncan it be done Laura Fygi (vo) Ruud Jacobs (b) Gwénaël Micault (key, accd) Phillippe Cathérine, Marcel Dorenbos, Francis Goya (g) Ferdinand Povel (sax, fl) Toots Thielemans (hmn) Peter Ypma (ds) Coen Van Baal (strings-arr) 1955�N�A���X�e���_���o�g�̔ޏ��́C�t�B���b�v�X�Ђ̏d�����������ƃG�W�v�g�l�̕�̊Ԃɐ��܂�C��A�t���J�ň�����ς���B���X�̏o���_�́C1980�N�Ɍ��������y�e���z�ŁC���̌����������̃O���[�v�y�Z���^�[�t�H���h�z�Ńq�b�g�`���[�g����킹���|�b�v�̎�B�����̃W���Y�̎�ł͂Ȃ����낤�E�E�Ƃ����̂́C�b�����l�q�̂Ȃ��A���Α����ɗ��������Ƃ���ł��B1991�N���\�̖{�Ղ́C����Ȕޏ��ɕ��������̃\����I�t�@�[�B�{���I�����_�ł͂T��������C�G�W�\���܂܂Ŏ�܁B���{�ł��V���������ٗ�̃q�b�g��ɂȂ�C�\���E�L�����A�̓������邱�ƂɂȂ�܂����B�W���Y�Ƃ͂قډ��̖��������ޏ����C�����l���Ă��������A���o������������́C��Ⴂ�ɂ��}�����ꂽ���҂̉��ȇM�ň�ڗđR�ł��傤�B�N���C�G�b�g�E�X�g�[���I�Ȃׂ����茷�V���Z�ƁC�ljƂ̐]�O�ޕ��Ȃ��炨�����ɂ��R�u�V�̉��Ȃ��̂���̑g�ݍ��킹�ŁC���ʂȂ�}�f�ȉ��̃��[�h�̗w�ɑ���Ƃ���B������~�����̂͏�Ⴂ�ɘr�̗������w�ł����B���̃s���E���R�u�X�̃��Y�������v���f���[�X���ďo�������C�J�e���[�k��V�[���}���X��啨���}���Đ��y��̊j����������`���B�����_�������Ȃ������̂������̔錍�B�O�E�F�i�G���E�~�R�[�Ȃ�A�R�[�f�B�I���t�҂̃A�����W���B�҂ł��˂��B�Ȃ܂��Ŕ���₨�e�������ɁC���͂̏����̒B�҂����ۂ����ƁB���[�h�̗w�Ɗ�����Ē����C����͊m���ɃG�W�\���܂ɒl�������ł��傤�B�������� |
 Spike Wilner Ensemble "Late Night Live at Smalls" (Fresh Sound
: FSNT 187) Spike Wilner Ensemble "Late Night Live at Smalls" (Fresh Sound
: FSNT 187)�@how am I to know �Ahopscotch �Ba gypsy without a song �Cbrown penny �Dthe intimacy of the blues �Eif you are but a dream �Fa blues of many colors �Ggo ask Ellis �Ha blues for another day Spike Wilner (p) Ian Hendrickson Smith (as, fl) Yves Brouqui (g) Paul Gill (b) Joe Strasser (ds) �u�������C����ȂƂ���Ƀw���h���N�\���E�X�~�X�N���I�v�Ƃ���ɍw�������{�Ղ́C�j���[���[�N�o�g�̒����s�A�m�e����2004�N�ɔ��\�����X���[���Y�ł̃��C�u�^���B���ۂ̃X�g���b�Z�[�̓��[�_�[�̃j���[�X�N�[������̓������ł����̂ŁC�X�~�X�̊�o�������N���X���[�g�q����ł��傤�B�w�����@�͐\���܂ł��Ȃ����Ȃ��ȃA���g�̂ق���������ł����C�꒮���炩�ɃX�C���O���ȑO�̃X�^�C�������[�c�Ɏ��������[�_�[�̃s�A�m�ɂт�����B�c�����ɃX�R�b�g�E�W���v�������e���r�Ō����̂��W���Y�̓�ꏉ�߂������ł�����C��������ʂ��Ƃł��傤�B���Z�ł̓s�[�^�[�E�}�[�e�B���ɏA���Ď�قǂ����C���_���ȃR���Z�v�g���z���B���̌�j���[�X�N�[�����y�@�i�݁C�E�H���^�[�E�f�C���B�XJr.�ƃW���L�E�o�C���[�h�Ɏt�������ق��C�W���Y�����Z���^�[�Ńo���[�E�n���X�ɂ��w�����܂����B���O�̖��m�W���v�������j�ɁC�����V���̃n�[�h�E�o�b�p�[���t�w���ł߂鋳������C���̂܂܉��ɂȂ����X�^�C���ł��B1989�N�̃����N�E�R���y�Ńt�@�C�i���X�g�C1993�N�ɃZ�~�t�@�C�i���X�g�ɂȂ������炢�ł�����C����Ȕ��͂Ȃ��C�y�Ȃ��n�[�h�o�b�v�ƃX�C���O���ȑO�̈ӏ����I���Ƀu�����h���ꂽ�y�Ȃ��܂��܂��ʔ�����ł����ǁC�Z�p�I�ɂ����ꐺ�ł����B���Y�������Â��悤�ŁB�A�b�v�e���|�̇@��F�ł́C���Y���̉��^�������イ�������Ȃ�C�u���������Ƃ���܂ŌÂ��ǂ�����̒H�X�����s�A�j�X�g�̃}�l����ł����������v�Ƃ����Ƃ������B����ɂ������Ē����Ȃ��̂͏W���B���ۂ̉����C���[�W���Ă̂��Ƃł��傤���C�ו��̉�����������C�����̋������s�A�m���ɒ[�ɍ��U���C�u�������Ȃ��E�E�v���Ċ����ł����B�����C�����������X�~�X�N�̃��[�_�[�Փ��l�̍��l�n�[�h�o�b�v�ʼn����B���[�_�[�����ɉ��C�s�[�^�[�E�o�[���X�^�C�����V�̃����f�B�b�N�ȃM�^�[�Ƃ��Ȃ��ȃA���g������N�C���e�b�g�̂T�Ȃ͈�ʂ���S���Ē����܂��B�������� |
| Other Discs |
 Jon Mayer "The Classics" (Reservoir : RSR CD 175) Jon Mayer "The Classics" (Reservoir : RSR CD 175)�@solar �Aalong came Betty �Blittle Melonae �Csouvenir �Drecordame �Esolid �Fvery early �Gecaroh �Hdon't misunderstand �Ivoyage �Jladybird Jon Mayer (p) Rufus Reid (b) Willie Jones III (ds) ���O�͂��傭���傭����������ɁC���[�_�[���^�ʖڂɒ��������Ƃ̂Ȃ��������[�_�[�́C1938�N�j���[���[�N�̓n�[�������܂�̃s�A�m�e���B�}���n�b�^���|�p���Z���o�ă}���n�b�^�����y��w�i�݂܂����C1950�N�㔼�ɂ̓v���ƂȂ�C1957�N�ɂ̓}�N���[���́w�X�g�����W�E�u���[�X�x�ɎQ���B���N�ɂ̓g���[���̐������݂ɂ��Q�����Ēm���x���グ�܂����B�r���E�G���@���X�̔��t�ŗL���ȃN�����l�b�g�̃g�j�[�E�X�R�b�g���C���̌�C�ɐ������̂��C�����B�������̐l���B�r�͂����ǂ�������ł��傤�B1960�N��ȍ~�̓T�h�������y�c�Ńs�A�m��e�����ق��C�f�B�I���k�E���[�E�B�b�N��T���E���H�[����̉̔����C�B���������L�����A��ς݂Ȃ���C�Ŕ��f����̂�������ゾ�����̂����[�_�[�Ղ͊F���B���̌�13�N�قLj����ނ��Ă��܂��C�������������ɉ����c���Ȃ������ܑ͖̂̂Ȃ������ł��˂��B���X�ɋ����\���čďo�������̂�1991�N�B1996�N�ɂ͂悤�₭�����[�_�[��\���C���̌�͍��܂ł��E�\�̂悤�Ƀ��[�_�[�Ղ�A���B�l���̏I�ǂɗ��āC�Q���z�̌��𗁂т��킯�ł��B�{�Ղ�2004�N�ɏo���g���I��ŁC�^�C�g���ʂ��C�̕t�����y�Ȃ��C�G�X�Ƃ����o�b�v�E�s�A�m�ʼn��t�B�꒮�C���U�{�A�̍D�݂��ǂ�������ނ̃s�A�m�́C���V���[�Y�ŕ����ꂽ���l�o�b�p�[�C���u�E�V���i�C�_�[�}���ƂƂĂ��ǂ����Ă���B���㑫�炸�ŒH�X�����C�R�e�R�e�̃o�b�v�E�s�A�m�ł��B�a�����n�������ɁC�]���E�肪�B�҂łȂ���Ζڂ����Ă��Ȃ��̂��o�b�v�B�ǂ�ȘV�Ԃ��������Ă���邩�Ɗ��Ҕ����ł������C���ʂ͑傫���O��ڂł��āB�Ƃɂ����~�X�^�b�`�����C���Y���̗֊s�͂����Ƃ��ƌn�B�����ꂵ�����Ƃ��т��������B���ɃA�b�v�E�e���|�̇@��B�C�I�͎S�邽��o���B�o���Ȃ��Ȃ疳������Ȃ�E�E�Ƃ��ߑ������o�܂���B�^����65�ł����炠����x�͎d���Ȃ���ł��傤���C�������V���̃G�f�B�E�q�M���Y��L���[����傾���Ă��ꂾ���I����������Ă��ł�����C������͒ʂ��ł��傤�B�������� |
 "Cyrus Chestnut" (Atlantic : 83140-2) "Cyrus Chestnut" (Atlantic : 83140-2)�@miss thing �Asummertime �Bthe journey �Celegant flower �Dnutman's invention#2 �Emy favorite things �Fany way you can �Gmother's blues �Hgreat is thy faithfulness �Istrolling in central park �Jsharp Cyrus Chestnut (p, rhodes) Ron Carter (b) Billy Higgins (ds) Anita Baker (vo) James Carter (as) Joe Lovano (ts) ���͂���R�ƙF��̎Y���Ƃ����v���ʁw���x���C�V�����x�̗]�C�����Ŕ��킳��Ă���C������T�C���X����B�o�邽�тɃT�C�h�������ς��̂����Ă��C�{�l�������藈�Ȃ���ł��傤�B�u�C������͂��{�l�̖��Ȃ����Ȃ��́H�v�ƁC���S�v����Ɏ�����{�Ղł́C�Ƃ��Ƃ����邩��Ɋ�Ȃ��������Q���̑�䏊�Ńg���I��g��ł܂��B����ς�ƌ��������Ƃ������C���ς�炸���{�l�̓S�X�y������N���X�I�[���@�[�܂Ŏ�L������o���ĎU���ƂȂ�C�~�������̂Ƀ}�b�V�u�C���B�����Ȏ��������E���ăe�N���������邲�{�l�̐S�̖��ɂ����C���t���C�����ɖ��Ղ��|���|������l�����ɁC�u�C�~�y�͂��������B�T�C�h���������Ȃ����l��I��ł܂��˂��E�E�B�t���[�L�[�łڂ��Ă菋�ꂵ���W�F�C���X�E�J�[�^�[�́C�h�X�������ďa�����ʁi���̎�̃t���[�܂݂̃��[�h�t�҂ɂ͑����ł����j�R���g���[�����G�ŁC�����������Ɏ��܂���B�������ő剻�����J������ł́C�A�g�����e�B�b�N�����g���[���t�@�̃����@�[�m�ƒ��X���~�B�Ȃ��Ȃ��������܂�����C�ꎞ���{�ł���ق₳�ꂽ�̂́C�ǂ��Ƃ��̃v���C�����l�������������C���̐l����̎��肾������ł��傤�B�ނ���{�Ղ̏E������̓A�j�^����ł����B���x�݂��Ă��ԂɁC����ȂƂ���ŃW���Y�E���H�[�J���̗��K�����Ă��̂��Ɩj�ɂށB�u���[�m�[�g�ւ̈ڐЂ̕����͂���ȂƂ���ɂ������킯�ł��˂��B�E�ȂC�o�J���ꂵ���N���C�G�b�g�E�X�g�[��������C�]���X���[�V�[�ŐL�ѐL�щ̂��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������� |
 "Bird - Original Motion Picture Soundtrack" (Columbia : CK 44299) "Bird - Original Motion Picture Soundtrack" (Columbia : CK 44299)�@Lester leaps in �AI can't believe that you're in love with me �BLaura �Call of me �Dthis time the drea's on me �EKo ko �Fcool blues �GApril in Paris �Hnow's the time �Iornithology �JParker's mood Charlie Parker, Charlie McPherson (as) Monty Alexander, Walter Bishop Jr., Barry Harris (p) Jon Faddis, Red Rodney (tp) Ray Brown, Ron Carter, Chuck Berghofer (b) John Guerin (ds) ����̓q�h�C�I�i�j�̂������玸���ւ����Ȃ��{�Ղ́C�_�[�e�B�n���[�ł�����݃N�����g�E�C�[�X�h�E�b�h���C���Ɏ���f��ɂ܂ł��Ă��܂����ē�i�w�o�[�h�x�̃T���g���ՁB���q�̃J�C������܂Ő��]���C�W���Y�t�҂ɂ��Ă��܂������炢�x�b�^���̃W���Y�I�^�������ނƂ��ẮC���̉f��ŃS�[���f���O���[�u�ē܂��l��C�n�C�\�̒��ԓ�����ʂ����Ė{�]��������Ȃ��ł��傤���B�̐S�̒��g�͂قƂ�NJo���Ă��܂��C�{�Ƃɂ��Ă͒ߕr�����C���ɂł����Ĉ�a���������o���Ă����t�H���X�g�E�E�B�e�J�[�����͈�ۂɎc��܂����˂��B1955�N�ɑ��E������傪�C���̌�o�Ă����{�Ղ̖ʁX�ƍ��؋������Ă���͂�������܂���B�p�[�J�[���̉e���҂͒N���ȁH�I���W�i�������̃R���s���ȁH���炢�����S���Ȃ��܂ܔ�������ł����C���ʂ͂Ƃ����ΐF�X�ȈӖ��ŁC�����Ƃ�̗\�z��h��ɗ���E���g��C�I�����̉�������p�[�J�[�����𒊏o���Ă����C�W�߂Ă����W���Y�����ǂ��ɔ��t������Ƃ����C�X�[�p�[�T�b�N�X���^���̗͋ƁI���t����������Ȃ������t�́C�ォ��T���v�����O�̊����Ɣ������h�肽�����Ă邼�I���ǂ�����ȍ��\����炩���̂̓e���r�̂����ԑg���炢�̂���ł��傤�B���C���̌��ɁC����̔��t�w���ǂ����Ă��^�C�~���O�����킹��ꂸ�C�i�T�P�i�C�قǂɂ���Ă����C�́C�F�X�ȈӖ��Œ�����������`�����E�֕��荞�ޕ��̃I�[���ɖ����Ă���B�������Ă݂�ƃW���Y�����h�ɐV���@�����Ȃ��Ƃ��݂��݊����B�[���猩��ƁC�����ɌQ����G���̏O�߂��Ċ��m�����m��܂���˂��B���������āu�����������I�v�Ɗ�������l�����Ă��C�������͂��`��ے肵�܂���B���̃A�i�N����Ɋ���ړ��ł��邩�ŁC�������傫���I�ԁB���ꂼ�u�^���|�p�v�̐��ł��傤�B������ |
�E�e�F2007�N12��23�� 23:35:55
|
�F�ɓ����t���̌����U�镑�������āC �N���X�}�X�E�C�u��ڂ̑O�� �L���X�g���ł��Ȃ������� �Ђ����玞�v���ɂގ����B �E�E�ӂƁC��ɕԂ�B �|�ނȂ����i�j�B ��������Ă���̂��C���́B
����Ɏ^�������|�\�l�͑����C �|�����g�����Ƃ��~�߂�ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
�ŋ߁C���X�ƐH���i�̒l�グ�������Ă܂��B �Ζ���g�E�����R�V�̍����͔R�����݂ł����B �����̒l�グ�������ł����ˁB ���[�}�E�N���u���\�������u�����̌��E�v�� �l�����I�O�ł����B�E�E���̏��͂łȂ���Ηǂ��ł����B  ���N�̎��́C�F�X�ƕω��̑傫���N�ł����� ���A�l�ŁC�傫�Ȑ��ʂ�����C��ɂ��邱�Ƃ��ł��܂����B �������Ȃ��炻�̗]�g�ŁC����̕M���肪���ɂȂ� �ǎ҂̊F�l�ɂ͐\����Ȃ����Ƃ�v���܂����B ���N�͖{�Ƃł���ɑ傫���ǂ��N�ƂȂ�C ��̗̈�ł��C�ЂƂ傫�Ȏd�����҂��Ă���܂��B ������ǂ��܂ŏ����邩���ڂ��܂��C �ׂ������ŁC�C���킸�Q�肽���Ǝv���܂��B ���������ǂ�������F�l�ɁC�{�N�Ō�̊��ӂ��B �F�l���ЂŁC�܂��V�N�ɂ��������܂��傤�B |
||||||||||||||||||
| ����ł͂܂����N�C �����䂤��������B |
||||||||||||||||||
| �Ձ`���h���@ | ||||||||||||||||||

����20�_�C����10�_�Ō��Ă�������
| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||
