
|
|
�u�����o�����CD�������v ���X�ꂵ�ݐH��������� �L���E���̂p�����ōς܂��Ă����� �h�{�����ŋ~�}�� |

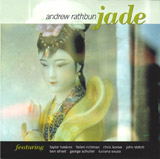 ���������� |
Andrew Rathbun "Jade" (Fresh Sound : FSNT 076CD) �@jade: I �Ajade: II �Bjade: III �Cjade: IV �Djade: V �Ejade: VI Andrew Rathbun (sax) Luciana Souza (vo) Taylor Haskins (tp) Helen Richman (fl) Chris Komer (hrn) John Stetch (p) Ben Street (b) George Schuller (ds) ���[�_�[�̃A���h�����[�E���g�u���̓g�����g�o�g�B���Z�ł̓����g���I�[���̖؊Ǒt�҃t�����N�E�������c�H���n�߁C�W�F�t�E�����O��p�b�g�E���o�[�o���Ɋw�сC��U�̓N�C�[���Y��w�i��Ő����w���U���܂����C���Ȃ����y�ւ̓]�������ӁB1992�N�ɓn�Ă��ăj���[�E�C���O�����h���y�@�i�݁C�C�m�����l���B���̌�̓u���b�N���������\���C���[����w�u�t�̖T��n���ɉ��t���������Ă��܂��B�{�X�g���ł��������ƂȂ�C���t���l�͐\���܂ł��Ȃ������@�[�m�ƃK�]�[���B������Ƃ��Ă��O�҂ɑ������Ă���͗l�B���t�̃t���[�W���O�ƃ��b�`�E�y���[�̃_���l�X����肭�ܒ������C�_�炩�ȉ��F���G�L�]�`�b�N�B�����ۂ��ł͓����̑��y�P�j�[�E�z�C�[���[���A�C�h���Ƃ��ŁC�B�҂ȍ�ҋȗ��V�ɕY��������ECM�̐������́C�ނ̍�i������ř������̂ł��傤�B�{�Ղ�2000�N�ɏo�����[�_�[����B�������S�ǕҐ��ŁC���{�l�̎����ȍ�ҋȗ͂������ɐ�������Ă���B��ނ𒆍��ɋ��߂��C�ɓ����@�ֈ����Ɉˋ������������C�u���[�m�[�g�V�嗬�h�̍ł����������Ƃ�����g���ė֊s���B�{�l�H���n�[�r�[�́w�X�s�[�N�E���C�N�E�A�E�`���C���h�x���͂炵���V�嗬�h��̋Â����A���T���u���ɁC�z�C�[���[�o�R�̐����ȓ]���Z�@���D�܂����F�𑫂��C���Ɏ����B�����������������C�G�L�]�`�b�N�ȘȂ܂���ۂ��ĉ̂����`�A�i���j���C���ꂵ���Ȃ�������[�_�[�̈Ӑ}���I�����O�B���[�W���E�}�X���t�����������Y�����ɃJ�i�_�̖���W�����E�X�e�b�`���n�[�r�[�C���̍D���ʼn�Y����B�ӏ��Ɖ��t���������Řa���B�q�h�C�\������͐M�����Ȃ��قǂ̍D���e�Ղł��B���E�߂ł��B |
![]()
| Recommends |
 Maurice Ravel "Bolero / Pavane pour une Infante Défunte / Concerto
pour la Main Gauche / Rapsodie Espagnole / La Valse" (Zig-Zag Territories
: ZZT 060901) Maurice Ravel "Bolero / Pavane pour une Infante Défunte / Concerto
pour la Main Gauche / Rapsodie Espagnole / La Valse" (Zig-Zag Territories
: ZZT 060901)Jos Van Immerseel (cond) Claire Chevallier (p) Anima Eterna �s���I�h�y����g���ĉ����̉��F�ɋɗ͋߂�����݂����C��������i�����ɔ��낤�Ƃ���u�����b�Z���̋����҃C���}�[�[�������1945�N���܂�B�̋��̉����A���g�E�F���y�����y�@�ŃP�l�X�E�M���o�[�g�Ƀ`�F���o���C�_�j�G���E�X�e���l�t�F���h�Ɏw���@���t�����������ł����C�I���K���̎t���͂��̃t�����E�y�[�e���X����ł����B���|���˂Ȑl�炵���C1972�N�ɕ�Z�Ń`�F���o���Ȃ̋����ɂȂ����ق��C�p�����y�@��A���X�e���_���E�X�E�F�[�����N���y�@�Ȃǂł����ڂ�����C���̖T��Êy�A���T���u���s�R���M�E���E���W�N���t��n�݂��Ďw���҂Ƃ��Ă������B�Êy��ɂ�郋�l�T���X���y���t�̐��E�ł͂��Ȃ�̗L���l�B�t�H���e�s�A�m�t�҂ł�����C����قǑf�G�Ƃ͂����Ȃ����̂̃h�r���b�V�[�̑O�t�ȏW��^������������Ă܂����B�{�Ղ́C����Ȕނ�1987�N�ɑn�݂����Êy�A���T���u���s�A�j�}�E�G�e���i�t�ɂ��2006�N�ՁB���������s���I�h�y��Ń����F��������w���I�Ȏ���̘^���ł��B�ǁ[���K�`�K�`�̃I�^�ȉ��t����Ɣ����^�J���������Ĕq�������Ƃ���C�ӊO�Ȃقǂ̍��i���Ղłт�����B�����悤�ȃX���[�Ƒ��߂̃e���|���Ńt�H���������C�ǂ��Ӗ��Ŋy�c�̐��\�Ɋ��|�������w���B�꒮�C�f���C�Ȃ��悤�ł��āC�N�����B�k���v�킹�邽���₩�ȋ���\���ƁC�v���ɍŒ���u���ꂽ�e���|�E���o�[�g�ōI�݂ɕω���t���Ă����B�ו��ɏh����̗͂ŁC�S�̂̑��e���`��낤�Ƃ������t�ł��낤�Ǝv���܂��B�u���[�W�F�̍ݏZ�I�[�P�X�g���ɂȂ��Ă��邾���ɃA���T���u���̗͗ʂ������C�Êy��̂��T�܂��₩�ȉ��F���C����̃I�[�P�X�g���ɂ͂Ȃ��݂��������B����̒���ɂ̂݊��|���邱�ƂȂ��C���t�̎����������^���͖ő��ɂ���܂���B���Ƀ����F���Ɏ��I���Ղ��������̕����C�꒮���鉿�l�͏[���ɂ���ł��傤�B���������� |
 Gabriel Pierné "La Musique de Chambre Vol.2" (Timpani
: 2C1111) Gabriel Pierné "La Musique de Chambre Vol.2" (Timpani
: 2C1111)Haoxing Liang (vln) Aleksandr Khramouchin, Vincent Gérin (vc) Kris Landsverk (vla) Catherine Beyon (hrp) Markus Brönnimann (fl) Christian Ivaldi (p) Quatuor de saxophones de Luxembourg ��ɃP�N�����Ƃ��^���ׂ��l�͂��邾��Ƃ����C�����锽�ʁC��x�ƂȂ��ł��낤�����y�S�W���C�S���g�̑啔�Ŏ��������j�C�ɂ͉��Ƃ����Ԃ����Ȃ��^���p�j�B���R�C�n�����w���҂Ƃ��Ắu��芸�����ꖇ�����Ȃ�C�ǂ�����H�v���S���ɂȂ�܂��傤�B�q�W���[�ɓ���I���ł��B���Ƃ����Ă�������ɂ́C���ŗL���ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��w�q�r�_�x�������C���炭���I�ɂ��m���x���猾���Ă��s�G���l�̑�\��ƌĂ�ō����x���Ȃ��w���@�C�I�����E�\�i�^�x�������Ă���B�����M�a�����@�C�I�����t�҂ŁC�t�����N�i��Ȉ����F���̃��}���h���Ȃ�T���Ȃ�C���̎��_�Ń`�F�������C���̑�͈��|�I�ɕs���ł��B�������C����ȊO�̊F�l�ɂ́C�����Ă��̓ڂ��ɂ��E�߂������B���̗��R�͂܂��C���t�B�O���ŏo�Ă���`�F���̃N�����[�V��������肢�B�w���@�C�I�����E�\�i�^�x�̃L���b�`�[���͂Ȃ�����C���Ȑ��ɂ����Ă̓s�G���l�L���̖��i�ł͂Ȃ����Ǝv����P�y�͂́w�`�F���E�\�i�^�x�́C�t�H���x���̖{���ՂƂ��[�����荇��������ł����C�}���R�́u�H�v�ȉ��t�����L���ɂȂ��w�O�d�t�x���₽�����Ȃ₩�ȘȂ܂��B�w���@�C�I�����E�\�i�^�x��������ɂ̓t���[�g�łŐe�ɍ̘^����C�|�Ĕłō\��Ȃ�������ƒ����܂��i���t�͍D���Ȃ�������ꐺ�j�B�����ЂƂ̗��R�́C�Ȃ����{�ՁC�唼��ӔN�̍삪��߂Ă��邱�ƁB�ڂɎ����ẮC�q�F�Z���ȃn�[�v�Ƒt�́u�����ȁv�ȊO�S�ĔӔN�B�t�����N�剺�̘g���ŁC�₪�ăP�N�����ɂ����������ȏ���ւƒH�蒅�����s�G���l�́C�^���h�i�ȃ|�X�g�E���}���e�B�X�g�Ԃ�𑶕��ɖ��킦��B�y���y�I���i�Ŗ���y�����ނ��C�Ō�ɂ͐l�m�ꂸ�����C��ȉƂɂȂ����E�E����ȁC�Â��Ȋ������L���邱�Ƃł��傤�B���������� |
 Claude Debussy "Préludes" (Talent : DOM 3810 04/05) Claude Debussy "Préludes" (Talent : DOM 3810 04/05)Daniele Callegari (cond) Royal Flemish Philharmonic �K�`�K�`�̃I���W�i���M��҂��Ă킯����Ȃ����̂̏����C��{�I�ɕҋȖ|�Ăɂ͂��܂苻�����������܂���ŁB�����ăs�A�j�X�e�B�b�N�|�p�̋ɒv�ł���w�O�t�ȏW�x�̊nj��y�z�u�Ȃ�āC�ǂ������N�ł��Ȃ����낤�Ɩ{�^���C���킸�ɉ߂��Ă���܂����B���ꂾ���ɁC�����Ăт�����ʎ蔠�Ƃ͂܂���������B�W���P�b�g�̕\���ɕҋȂł͂Ȃ��s�č��(Recomposition)�t�Ǝ��M���X�C���ł̂��ɒB�ł͂���܂���ł����B���̍���Ȏ��Ƃ�S�������̂̓����b�N�E�u���E�F�C�Y(Luc Brewaeys)���B1959�N���܂�̔ނ́C�u�����b�Z�����y�@�ŃA���h���E���|���g�Ɏt���B�ꎞ�̓N�Z�i�L�X�Ƃ��𗬂����x���M�[�̌��㉹�y�Ƃł��B�P�N�������ƌ������قǂ��ґz�����߂��u��̏�̑��Ձv�̊ɑt���C�w���E���@���X�x�����ڂ���u�����̌������́v��忓����C�u���߂鎛�v�𖢒m�Ƃ̑����Ɋ����Ă��܂���_�ȃf�t�H�����́C�ҋȂƂ͎��Ĕ�Ȃ�n���I�ӎu�Ɉ��Ă���B�����𗘂��ď[���ɉ�����L���C���Ȃ̂��p�[�J�b�V�u�ňً��k�I�ȉ����̘A�Ȃ�Ƃ��ꗂ����������ƂȂ��C�ɂ߂Ď��R�Ɋnj��y�z�u�̃��]���f�[�g�����咣�B�܂��ɍč�Ȃ̖��ɒp���Ȃ��M���ł��B�ҋȂƂ��Ă������Ɋ����x�̍������ނɓ���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���t��2002�N����J���K���������Ȏw���҂Ɍ}���C��f�������t�����h���ǁB���x���������������ƂȂ��B�|�Ă��̂Ȃ�ď��F����������x�̔F�������Ȃ��������ӂ������C�{�ՂɊւ��Ă͗�O�B���E�߂������܂��B�ǂ��ł��B���������� |
 Maurice Ravel "Alborada del Gracioso / Rhapsodie Espagnole / Daphnis
et Chloé / La Valse / Pavane pour une Infante Défunte / Bolero"
(World Wind Music : WWM 500.086) Maurice Ravel "Alborada del Gracioso / Rhapsodie Espagnole / Daphnis
et Chloé / La Valse / Pavane pour une Infante Défunte / Bolero"
(World Wind Music : WWM 500.086)Norbert Nozy (cond) Royal Symphonic Band of the Belgian Guides �W�����Q���̐��t�����Ȃ𐁂�����ł��ꂽ�A���K�^�[�C�����Ƃ��đN��ɔ]�֍��荞�܂ꂽ�m�W�[����Ɖ��������̐��t�y�c�Ƃ����C�Z�ʂ̍��������邱�ƂȂ���C���₩�Ȃ��ȂƗ}�g�������C�u���X�o���h�Ƃ͎v���ʂقǖL���ȋ����Ő��t�y�t�@���𗸂ɂ�������ł����B�ނ�̉����͑唼�����l�E�K�C�[���烊���[�X�B�ق�̐��N�O�܂ł͑���Ȃ��A���ՓX�Ŕ�����C���̒�ԃu�����h�i�ł����B�Ƃ��낪�s�K�ɂ��C���̔Ō����h��ɓ|�Y�I�����H�����ނ�̘^���́C�唼�����莊��ɂȂ��Ă��܂��܂����B����ł��C���E���w�̋Z�ʂ��ւ�o���h�����ɐɂ����Ǝv�����W�҂�����������ł��傤�B���N�����Ȃ������ɁC������������J���⡂̔@�������Ղ����ɏo�Ă��܂����B2003�N�ɏo���{�Ղ����̗ǂ���ŁC���Ƃ�1998�N�ɐ������܂ꂽ���l�E�K�C�[�Ղ��Ĕ��������̂ł��iRené Gailly: CD 87146�j�B����ΕҋȂ��̂Ȃ킯�ł����C�����Ă݂�ƁC���ӂ����ɂ͒����߂����Ă��܂��قǍI�݂ɖ|�Ă���Ă��Ăт�����B������C21���I�l�ɂ��s�ċz�̍���Ȃ��t����y�ҋȂł͂Ȃ��C������l�́i���ɂ̓����F������_�ߌ��t�܂Œ��Ղ����j�R�����镈�ʂ�T���o�������J�Ȏd���Ԃ�̂Ȃ���킴�ł��傤�B�L���Ő��k�Șa�����o���ւ郉���F���̊nj��y��i�����ɁC�M�h���t���̉��C�����Ղ�̃��b�`�Ȗǂ��ǂ������Ă���B�u�����t�v��u�_�t�N�����g�ȁv�̝{���Ȃǂɏo�Ă���C��̝��肻���ȓ����������C�����܂��Y��ɐ���������Ƃ́B�������ɁC�A���K�^�[�C�C���ɂȂ��ĎQ��܂��B�nj��y�̗R�s�[�ɗ��܂炸�C���Ƃ��Ă����F�Ȃ��B�����F���D���̕��Ȃ�C�����đ��͂��Ȃ����^���Ȃ̂ł́B���E�߂ł��B���������� |
 Magnus Lindberg "Clarinet Concerto / Gran Duo / Chorale" (Ondine : ODE 1038-2) Magnus Lindberg "Clarinet Concerto / Gran Duo / Chorale" (Ondine : ODE 1038-2)Kari Kriikku (cl) Sakari Oramo (cond) Finnish Radio Symphony Orchestra ��Ȏ҂�1958�N�w���V���L���܂�B�V�x���E�X���y�A�J�f�~�[�Ń��E�^���@�[���ƃw�C�j�l���Ɏt�������̂��C1981�N�Ƀp���֗��w���C���B���R�E�O���{�J�[���ƃW�F���[���E�O���[�C�ɂ��w��œ��p��\���܂����B�T���l����T�[���A�z�ƂƂ��Ɏt���̌O���������ɎC�s�����J���I�t�Ȃ�C�����Ƀ��o���`�ȓ��l���g�D�B�����͂��Ȃ�����I�ȉ��y�������Ă����炵���̂ł����C�₪�ĐV�ÓT�I�ȌX���ɉ�A���ĉ����ɂȂ����͗l�ł��B2005�N���\�̖{�Ղ́C����������̌�̍�B�ޓI�ɂ͍ł�������₷���nj��y�Ȃ��O�i���^����Ă��܂��B�t�B�������h�l�炵���C�ނ̃��Y���ɂ͂�茴�n��`�I�ȃS�c�S�c��������C����������I�B�����C����������Θa���ɂ̓t�������c�I�����т₩����A�a�ȂƂ��̃P�N�����I�ȑ@�ׂ�������C�Ȃ��Ȃ��ɃJ���t���B�߂��Ƃ����T���Ȃ�C�����̖�����Ɓi�m���h�O�����Ƃ��́j�ڐ�����C��≸�₩�ɂȂ����ӔN�̃I�A�i�����ߒ������悤�ȏ��@�ł����B������͂��Ȃ�I�т܂�����ǁC�f���e�B�[����I�A�i���ă}�]���Ă�M���Ȃ���v�ł��傤�B�{�Ղ̂����ЂƂ̖��͂͗D�ꂽ���t�Ƙ^���B1960�N���܂�̃\���X�g�͍�Ȏ҂̉��厞��̌�y�B�ނ̍�i�𑽂��������Ă��閿�F�ŁC�w�N�����l�b�g���t�ȁx�̔팣��҂������ȁB�̂��C�M���X�ɗ��w���A�����E�n�b�J�[�ɂ��t�����܂����B���㉹�y���Ŋ������Ă��邹�����m���x�͖F�����Ȃ��ł����C����t�@���Ă���ɂ���������ȕ��ʂ��C�y�₩���~�₩�ȉ��F�Ő�������Z�ʂɊ��Q���܂��B���̊nj��y�w���ǂ����������Ă��Ă������ł��B���������� |
 Gabriel Pierné "La Musique de Chambre Vol.1" (Timpani
: 2C1110) Gabriel Pierné "La Musique de Chambre Vol.1" (Timpani
: 2C1110)Philippe Koch (vln) Aleksandr Khramouchin, Vincent Gérin (vc) Ilan Schneider (vla) Thierry Gavard (b) Étienne Plasman, Markus Brönnimann (fl) Philippe Gonzales (ob) Olivier Dartevelle, Jean-Philippe Vivier (cl) David Sattler, François Baptiste (bssn) Miklos Nagy (hrn) Adam Rixer (tp) Gilles Héritier (tb) Julia Knowles (p, hmn) Christian Ivaldi (p) Rémy Frank (recit) Quatuor Louvigny ���p���c���R�Ƙ^�����C�f���|���Ɍ��āC�����ɕ��ߑ�̌���ׂ��Ă����^���p�j�B���x�͉��ƃs�G���l�̎����y��S���ɑS�W���B�܂����C���ԓI�ɂ͌y�������̃s�G���l���C�����܂ł܂Ƃ܂����`�ɂ��Ă����Ƃ́B���l���̑������{�ł�����C����Ŕނ̕]���������ς��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�{�Ղ͂��̑�ꊪ�ɂ�����C�O���̓��@�C�I�����𒆐S�Ɍ��y��̂��߂̊y�ȏW�C�㔼�͊e��NJy��̂��߂̏��i���W�߂��Ă���B�L���Ȃ������C�������߂Ē������̂������ł��B�������ɍ����ȁw�\�i�^�x�̏o���͌��o���Ă��܂����C����ȊO�ɂ������ƌ��鏬���ȉ��i������U����Ă���C�E�n�E�n������B�u�p���Ќ��E�C���̃T�������y�������w���ҁv�C���[�W�̉A�ɉB������Ă����p���C���������Ղł���B���������ɂ����Ƃ��낪����Ƃ���C�����͂����t�w�ɗ���Ȃ����Y�����ƁB�唼�̋ȂŃt�����g������̂̓��[�r�j���C�l�d�t�c�ƁC���̑�ꃔ�@�C�I�����̃t�B���b�v�E�R�V������B�t����������Ă��ꂽ�ނɕ��匾�����Ⴀ�����Ȃ���ł����ǁC�����͂��e�t���[�Y�̓��蔲�����щH�����C�����͂��t���b�g�C���̂��߂��C���F�ɋ͂��Ȃ����݂�����̂��ܑ̂Ȃ��B�l�d�t�c�����̂���ɔ�ׂ�ƁC�����s�b�`�s���肩���m��܂���B�ނ��C�����ƌĂ�ł������x���Ȃ������ł̂��Ƃł�����C�ґ�Ȃ�ł��傤�B���܂��������f�B�A�p�]�����̋C�����C�������ɂ�ǁ`��������܂��B�����܂ł܂Ƃ܂��Ē�����@���x�Ɩ������Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ��B�h�r���b�V�[�O��̃��}���e�B�V�Y��������݂������́C�����Ƃ��Ă��[�������߂ɂȂ鉿�l���������܂��傤�B���������� |
 Florent Schmitt "Psaume XLVII / Suite sans Esprit de Suite / La Tragédie
de Salomé" (Hyperion : CDA67599) Florent Schmitt "Psaume XLVII / Suite sans Esprit de Suite / La Tragédie
de Salomé" (Hyperion : CDA67599)Thierry Fischer (cond) Christine Buffle (sop) The BBC National Orchestra and Chorus of Wales �V���~�b�g�v��50�N�͂܂���N��Ȃ̂ɁC�v�킸�t���C���O�����Ƃ����v���Ȃ��{�^���B�w���҂��I�P���t�����X�Ƃ͑S�R�ړ_���Ȃ��E�F�[���Y�n������C�������{�i�I�ȃV���~�b�g��i�W���o�Ă���Ƃ́C���߉ޗl�ł��������Ȃ��������Ƃł���܂��傤�B�����Ց����̑g�ȔŁw�T�����̔ߌ��x�́C����ł������p���[���������^�ŁC�t�H��������I�B�����W���Ƃ������ّ��Ȃ��炢������܂����C������ƃA�[�e�B�L�����[�V�����̑�������Ȃ��Ƃ��낪���邩���m��Ȃ��B�z���X�g�̘f���ɓ������`�[�t���o�Ă���u�O�t�ȁv�́C���������F�������~�����ȂƂ̕s��������܂��B����ł��C�������E�F�[���Y���̋Z�ʂ̓}���R�ՂƂ͔�ׂ���ɂȂ炸�C�����Փx���i�W�ł��邱�Ƃ̗L���݂���������C�[�����E�߂ł�����̂ɂ͂Ȃ��Ă���܂��傤�B���ꂾ���ɐɂ����̂́C�}���e�B�m���Ƃ菟���̊�������w����47�x�ł����B�I�P�͐��\����낵���̂ɁC���œ��������̍��������������s�����̗ь�N�Ȃ�ł����˂��B�ǂ��̔�]��������i�t���V�[�����炦�Ȃ������݂����ł����ǁC�����̑唼�����e���ȍ������ɂ���̂͊ԈႢ����܂��܂��B����ȃC�}�C�`�N�ɂȂ��l�c�����H���ăA���^�C�u�����������Ă����B�܂Ƃ��ȉ��t�Œ����������̂Ȃ����ȁw�֘A���̂Ȃ��g�ȁx�����ƃI�P�����̔����Œ����C���܂��ɃV���~�b�g�Ȃ�ł͂̋ɍʐF�{�ً��k�ϔ��q���ڂłނ���I�C�V�C����Ɍ��܂��Ă����Ȃ��ł����B�w���t�I�����ȁx�قǂ̃n�C�e���V�����ł͂���܂���ǁC�ނ̎��D���Ȋnj��y�@�̐����l�܂������i�B������������Ŕ������b��͏\�ɂ���܂����˂��B���������� |
 Andrzej Panufnik "Sinfonia Sacra / Sinfonia Rustica / Sinfonia Concertante"
(EMI : 0946 3 52289 2 2) Andrzej Panufnik "Sinfonia Sacra / Sinfonia Rustica / Sinfonia Concertante"
(EMI : 0946 3 52289 2 2)Andrzej Panufnik (cond) Aurèle Nicolet (fl) Osian Ellis (hrp) Menuhin Festival Orchestra : Monte Carlo Opera Orchestra ��Ȏ҂�1914�N�����V�������܂�B�����V�������y�@�i�̂��C1937�N�Ƀh�C�c�֗��w���ă��C���K���g�i�[�Ɏw���@���w�сC�L�����A�̏o���_�̓N���R�E�ǂ̎w���ҁB�̂������V�����E�t�B���̉��y�ēƂȂ�C�x�������E�t�B������h���ǂ̋q���w���҂Ƃ��Ċ��܂����B�قǂȂ�1947�N�ɃV�}�m�t�X�L��ȏ܁C1949�N�ɃV���p����ȏ܂���܂���ȂǍ�ȉƂƂ��Ă��]�����ꂽ�ނ́C���Y��`��������1953�N�ɓn�p�B�����A�J�f�~�[���_����̂ق��C1991�N�ɂ̓i�C�g�̍��܂ł��炢�C�㔼���͎�����p���l�Ƃ��Đ����邱�ƂɂȂ�܂����i����Ŗ{�Ղ̕\���ɂ́u�C�M���X�̍�ȉƁv�ȂǂƏ�����Ă���̂ł��傤�j�B�������̍�ȉƂɓ��L�̎����Ȃ̂����m��܂��C���̐l���a�����a�܂���̂��I����ȉƂ��Ȃ��Ƃ�����ہB�w�t�̍ՓT�x����C�₽������I�ȃ��Y���������������Ċȑf���B����l�`�̗x��ɂ������������Ȃ������̔����ɏ��C���ǂ̔{�����ʂ���g�����a�ݘa�������X�ɌJ��o���āC�Â���L�f��̔@���ߑs���܂݂̗E�s������܂��܂��B�T�X�����l������̈����́C�t�����X�Ȃ�I�l�Q���̌����ȕӂ�ɂ����Ă���B�������C�����������ɔނ̂���͂����Ɠy�L���C���Y�����L�̗₽���d�������������I�B����ş����̗����Ȃ����Ǝv���C�S�Ă��s���@�Ȃ�ł��傤����ǁC�w�c�ɕ��x�̑�O�y�͖`���̈Ќ��ɖ���������́C�t�����X���̂ɂ͂܂��������Ƃ̂Ȃ��d�X���������C�Ȃ��Ȃ��ǂ����Ĉ����Ȃ��ł��B�X�g�����B���X�L�[�����v�ȕ��Ȃ�C���قLj�a���Ȃ���Ȃ��ł��傤���B�l�����I�ȏ�O�̘^�������ɁC����̂��̂قǂ��Ȃ�Ă͂��Ȃ����̂́C���t���ǎ��ł��B�������� |
 "Messe en l'Honneur du Saint-Sacrement / Deus Abraham / Pie Jesu /
Quid sum Miser? (Jongen) Missa Festiva (Peeters)" (Hyperion : CDA67603) "Messe en l'Honneur du Saint-Sacrement / Deus Abraham / Pie Jesu /
Quid sum Miser? (Jongen) Missa Festiva (Peeters)" (Hyperion : CDA67603)David Hill (dir) Paul Provost (org) Thomas Gould (vln) The Choir of St.John's College, Cambridge : London City Brass �������ɃW�����Q���E�N���X�����I�������L���ɂȂ��Ă������̂́C�@����i�܂ł͎肪��炸�C�x���M�[�ߑ�̍�ȉƂ͍����唼�������@��Ԃ̂܂܁B����ȏ������˂Ă��C�p����Ƃ̃n�C�y���I�����o���T�[�r�X�B�d���̏@����i��^�����܂����B���ɃW�����Q���̏@���Ȃ͂܂Ƃ܂��Ę^�������@��ő��ɂ���܂���̂ŁC��ϋM�d�B��т����̂͐\���܂ł��������܂���B���̒m�V�̉������s�����W�����Q���ƁC�ނɔ���]��I���K�����t�Ȃ��������y�[�e���X�B�Ȃ������낤�͂����Ȃ��C�c����͉��t�̃��x���ɐs���܂��傤�B�����̓Z���g�E�W�����Y�E�R���b�W���̑����S���B�V���̃n�C�y���I�������ɗǂ��m�F�������������̂́C�ǂ��ǂ��l����ƃZ���g�E�W�����Y���̑����āC�i�N�\�X����o���t�B���W�̍����ȏW�𐁂����Ƃ���ł����˂��B���Ȃ݂ɂ�������ɓ��ꂽ�Ƃ��̈�ۂ́u��w�T�[�N���̍����c���x���ɗ��܂��Ă���C�v���Ƃ��Ę^������ɂ̓L�����e������v�ł����B�q�h�C�b�i��j�I�n�C�y���I�����ʂŋ@�ނ��䍂���ɂȂ����̂��C���̌�撣���ė��K�����̂��C�����͐������܂��ɂȂ��Ă�����̂́C�s�����̗ь�Ԃ�͉B���悤���Ȃ��C���������̊��ɂ�␅���������͎̂c�O�ł����B�p���@�[�k�Ղł����W�����Q����m�炸�C���������Ȃ��Ǝv���Ă���l���C�N�����Ղł����y�[�e���X��m�炸�C���������Ȃ��Ǝv���Ă���l�C�\������x�ɕ��^���ꂽ�W�����Q���̏@�����i�������l�i���킽���j�ȊO�́C�����Č���ɂȂ�قǂ̂���ł͂Ȃ������m��Ȃ��ł��˂��B�������� |
 Lex Van Delden "Quartetto, op.58 / Sestetto, op.97 / Duo, op.27 /
Introduzione e Danza, op.26 / Nonetto per Amsterdam, op.101" (MDG
: 603 1317-2) Lex Van Delden "Quartetto, op.58 / Sestetto, op.97 / Duo, op.27 /
Introduzione e Danza, op.26 / Nonetto per Amsterdam, op.101" (MDG
: 603 1317-2)Viotta Ensemble ��Ȏ҂�1919�N�A���X�e���_���o�g�B�ꂩ��s�A�m���w�̂�11�˂����Ȃ��n�߁C�w�ǐ��K�̋���͎ʂ܂܃v���ɂȂ�܂����B1938�N�ɃA���X�e���_����w�i�ۂ��C��U�͖�w�B�w�Ƃ̖T��C1940�N�ɂ̓v���̍�ȉƂƂ��ď�����\���Ă��܂��B����ɂ������N�Ƀi�`���I�����_�N�U�B�ނ͂Q�N��ɂ͊w�Ƃ̒f�O��]�V�Ȃ�����܂����C���̌�̓��W�X�^���X�����ɐg�𓊂��ďI��ɁB�{���A���N�T���_�[�E�Y���[�v���C���b�N�X�E���@���E�f���f���ւƉ��������̂��C���̃��W�X�^���X�����̌̂ł����B1948�N�Ɏs���y�܂�^�����̋��������C�ŏ��ɔނ�]�������̂��ފ݂̖k�J���t�H���j�A�E�n�[�s�X�g����ŁC�ނ炪��Â����ȃR���N�[���ɂ������x�̗D���������̂́C�����ɐ����I�ȈӐ}�܂݂������̂����m��܂���B����̊��ɁC�ނ̏��@�͉����B�֊s���̂��̂̓��}���h���ł���Ȃ���C�������_���n�̃V���[���z�t��E���}����ɒʂ���s���Ȑ��@�\���ƃO���e�X�N�ȓ]���Z�@��}���B���̃O���e�X�N�ȍ��_�����i�ƂȂ�{���ɕs���ȉe�𗎂Ƃ��Ĕނ炵�������o���܂��B�����̓I�l�Q���X�e�B�b�N�ȉA�T���������܂��C�t�����X�I�ȗ��킳�����������u���Ă��܂����ǁC�������͂����Ƃ���C�w���y�Z�d�t�ȁx�Ȃǂ͉A�C�ȑO�����}���h�l���Ƌߑ�̘a�����D�܂����a���B�Ȃ��Ȃ��ʔ��������܂����B���t���郔�B�I�b�^�E�A���T���u����1992�N�ɁC�R���Z���g�w�{�E�ǂ̒c�����W�܂��đn�݁B�Ƃ낯�����ɓ����x�����������g���[�h�}�[�N�̃R���Z���g�w�{�E�c������ɂ��ẮC��╗�����̂����Ƃ�����ۂ͐@���Ȃ����̂́C���������̃��x���̓L�[�v�B���̖�����Ƃ̉��y�I�L�����N�^�[�������Ƙ��Ղ���ɂ͏[���Ȃ̂ł́B�������� |
 Gustav Holst "The Planets" (Chandos : CHAN 6633) Gustav Holst "The Planets" (Chandos : CHAN 6633)Alexander Gibson (cond) Royal Scottish National Orchestra and Women's Chrous 1995�N�ɐɂ����������������M�u�\�������1926�N�X�R�b�g�����h�̃}�U�[�E�F�����܂�B�����X�R�b�g�����h���y�A�J�f�~�[���o���̂��C1957�N�Ɏj��ŔN���ŃT�h���[�Y�E�E�F���Y�����̌���̉��y�ēɂȂ�C�Q�N��ɂ͖{�Ղł��������Ă���X�R�b�g�����ǂ̎�Ȏw���҂֏A�C�B1984�N�܂ł̒����ɓn���ē��I�P����������܂����B�X�R�b�g�����h�̌���̑n�݂ɂ��v�����C�ŏ��̉��y�ē����ȂǍv�������������̂��C1977�N�ɂ̓i�C�g�̍��B1979�N�ɃO���X�S�[�Ő������܂ꂽ�{�Ղ͔ӔN�̘^���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�킴�킴�Ĕ�������炳���G�G���Ɩ����݂ɍw��������ł����E�E�B�����\���グ�āu������ǂ��w���҂ł����˂��H�v�Ƌ^�╄�����c��܂���ŁB�l�����I�O�̘^��������������Ƃ��Ă��C�Ǖ��ƌ����̓��蔲�������܂ЂƂ����Ă��܂��C���ɊǕ������肷���Ƃ����܂����C���ߕs���B���܂��ɂ��̊Ǖ��𖭂ɂł������^��������Ă����ł�����C�����イ���t���d���O�̂߂�ɂȂ����Ⴂ�܂��āB������^���s���̃��^�{���b�N�Ȃ����l�������C�q�ǂ��̑O�ŃG�G���������悤�ƁC�낭�낭�����^���������^����̓k�����ɏo�ẮC�Ԃ��܂ɑ������ꂳ���Ă����]��ł�p�B���傤�ǂ���Ȋ����̉��t�ɂȂ�������Ă܂��B����ł��C�V���̃X�R�b�g�����h�̈АM���������������B�Z�ʂ͓����Ƃ��Ă͍����ł����C����Ȃ��Ă��ǂ��Ɋy�͂ł͂������n�B�̋Z�B���̒�t����L���ɖ炷�u�ΐ��v�̏d���ȕ��͋C���Ɋւ��Ă͂Ȃ��Ȃ��ǂ����āC�����Ȃ��̂ł��B�f���I�^�ȊO�̑命���̌��S�ȃt�@���������Ĕ����قǂ̂��Ⴀ�Ȃ��ł��傤����ǁC��������������E���Ă�����̂��ꋻ�Ȃ̂ł́B�������� |
| Other Discs |
 "Clarinet Quintet in G Major (Somervell) Clarinet Quintet in G Minor
(Jacob)" (Helios : CDH55110) "Clarinet Quintet in G Major (Somervell) Clarinet Quintet in G Minor
(Jacob)" (Helios : CDH55110)Thea King (cl) The Aeolian Quintet ����҂Ƃ��ĉp�ߑ�̑b��z�����X�^���t�H�[�h�B���������ɂ́C�L���l������Ζ����l�������킯�ŁC�{�Ղ͂��Ȃ��҂̕��ނɑ�����Q�����������N�����l�b�g�d�t�Q�i�^�������̂ł��B�w���I�X�̓n�C�y���I���̗����Ő�ȁB1979�N�Ƃ�������ɁC����Ȃ��̂𐁂�����ł����Ȃ�āC�ɒB�ɉp���~�ՋƎ҂̒��_���ɂ߂Ă͂��܂���ȂƊ���������ꂽ����ł��B�\�}�[���B����1863�N�E�B���f�����[�����܂�B�P���u���b�W�ŃX�^���t�H�[�h�C��������Ńp���[�Ɏt�����C1894�N���瓯�Z�����B1901�N����͋���R�c��̎��w���߁C��狳�用�ł̂ݖ����c�����l���B������W���R�u�͉��������1924�N����1966�N�Ɉ��ނ���܂ŋ��ڂ�����C�}���R���E�A�[�m���h��C���W�F���E�z���X�g����琬�B����������㉹�y�܂�������̎���ɔw�������C�������ێ�h�̖������������܂����B�{�Ղ̘̍^�Ȃ��C�O�҂�1913�N�C��҂�1942�N�̍�B�ɂ�������炸�̒����w���������Ƃ���C���@�͂̂�т肵���O�����}���h���V�B�����܂Ń��C���̓u���[���X����f���X�]�[���̔��ӎ��ł��B���ɑO�҂͌Â߂������C���^�ʖڂ��̂ɓ˂������Ȃ��Ƃ��������Ȃ�ł��傤���C���y�ɑO�ƌ�낪�Ȃ��Ȃ�������́C�l����낾�������ƂŖ����ꂽ����������i���Âɕ]���ł���Ƃ����_�ł́C��������Ȃ̂ł́B�������ɑ��펞�ɏ����ꂽ�W���R�u�̑�O�y�͂Ȃ́C���[�������ً̈��k��������C�ߑ�t�@���ł��[���ʔ���������B���̔��������͒S�ۂ���Ă���܂��傤�B�\�������L���O���j�͓����M���h�z�[�����勳���B�ӂ���_�炩�����F�̔�����W�J���j�ɂށB���ꂾ���ɐɂ����̂͌��̂S�l�ł����B�W���P�b�g���̂܂ܒ��Ղȓc�ɏ�ň����Ȃ����ʁC���ɑ�ꃔ�@�C�I�����̃s�b�`���������C�����f���X�]�[�����Ȃ��炻�ꂪ�ڗ��\�}�[���F���̌d�t�ȂōC�������Ȃ�����������o���Ă��܂����̂͐ɂ����ł��˂��B�������� |
![]()
| Recommends |
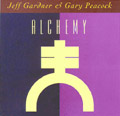 Jeff Gardner & Gary Peacock "Alchemy" (Jeff Gardner-Universal
: 983 765-6) Jeff Gardner & Gary Peacock "Alchemy" (Jeff Gardner-Universal
: 983 765-6)�@alchemy �Acoisa do Rio �Bstories untold �Cline for Tommy Flanagan �Dwaiting for you �Eangel �Ffor Duke and Strayhorn �Gcity at the bottom of the sea �Hbetween our hearts �Izero gravity �Jdancarina �KMaastricht �LSelva Jeff Gardner (piano) Gary Peacock (bass) 2002�N����̓u���W���ɋ��_���ڂ��C���y�I�ɂ��u���W�����̓x�����������Ȃ����W�F�t�E�K�[�h�i�[����B�G���@���V�X�g�̍���ȏ���ƃ{�b�T�o�R�̟������a�����a�������Ƃ���ɁC���̐l�̎������̑���������̂͂����m�̒ʂ�B���t�ʂł��O�A������ׂ��L���L���t�@�ɓ���������C���^���̗������������Ⴉ�����D�ރX�C���K�[�ł͂���܂���B��ȃZ���X���ǂ��l�Ȃ̂ŁC�u���W���ɌX�|���悤�Ɨǂ��ɂ͈Ⴂ�Ȃ���ł����ǁC�T�C�h��������W��܂Ńu���W���܂݂�ɂȂ��������̘^���́C���ʂƂ��Ĕނ̃s�A�m���猄�Ԃ�D���C���t������{���q�ʼnA�e�̖R�������̂ɂ��Ă��܂��Ă���̂��m���B��a�����������ɂ͂���܂���B�{�Ղ�1990�N�C�܂������̃K�[�h�i�[���C���Q�C���[�E�s�[�R�b�N���}���Ď��吧�삵����d�t�B���e�����y�ւ̌X�|�͖��t�����x�ɗ��܂��Ă���C�����قǃG���@���X�I�B�꒮�����܂��]���Ƀf�j�[�E�U�C�g�����̖��O����������͎̂������ł͂Ȃ��ł��傤�B�U�C�g�����͖{�Ղɐ旧����7�N�C�`���[���[�E�w�C�f�����}����ECM�Ɂw�^�C���E�������o�[�h�E�E�x��^���B�{���ɍ̘^�������C�X�E�G�T�́u�h���t�B���v���C�o���s�o�������Ƃ���ŔN�Ⴂ�K�[�h�i�[�̐S�𑨂����ł��낤���Ƃ͑z���ɓ����܂���B���ہC�����ł̃K�[�h�i�[�͂܂�܁C�U�C�g�������V�B17�N�O�ɘ^���������吧��̃f���I�^�������̃^�C�~���O�ōĔ�����C���̍Ĕ��ɖz�������̂����j�o�[�T���E�t�����X�x�Ђ̃_�j�G���E���V���[������i���t������Ɠ����j�������Ƃ����̂́C����Ӗ��Ƃ��Ă��Ӗ��[�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B������������Ƃ͂����C�^���̓N�����g���E�X�^�W�I�ŃW���E�A���_�[�\�����S���B���t�Ƃ��ǂ��C�ނ̑O�������\����ɑ���ǎ��ȃf���I��ł��B���������� |
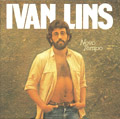 Ivan Lins "Novo Tempo" (Odeon-EMI : TOCP-66066) Ivan Lins "Novo Tempo" (Odeon-EMI : TOCP-66066)�@arlequim desconhecido �Abilhete �Bsertaneja �Cbarco fantasma �Dsetembro �Enovo tempo �Fcoragem, mulher �Gfeiticeira �Hvirá �Icoração vagabundo Ivan Lins (vo, g, p) Gilson Peranzzetta (arr, key, acdn) Vitor Martins (lyrics) et al. �Ԃ�������̑�ƃW���r���������C�u���W���ł����w�̒m���x���ւ�C���@���E�����X�B1945�N�ɐ��܂ꂽ�ނ́C12�Ŏm���w�Z�i�݁C���t�y���ʼn��y�Əo����Đl����]���B�Ɗw�Ńs�A�m���C�����C�{�T�m���@��n�ނ悤�ɂȂ����ނ́C�H�w���w�ԖT���Ȋ������J�n�B1969�N�Ƀ��I�f�W���l�C���A�M��w�ōH�Ɖ��w�̊w�ʂ邢���ۂ��C�G���X�E���W�[�i�Ɏ���Ȃ���āC�ŏ��̐�������ɂ��܂��B��1970�N�ɑ�5�ۉ̗w�t�F�X�e�B�o��(FIC)�ŏ��D���B1974�N�ɂ́w���[�h�E���[�����x�̃q�b�g�Ől�C���l�����܂����B1980�N��ɂ́C�N�C���V�[�E�W���[���Y����F�߂�ꂽ�u���F���X�v�ō��ۓI�ɂ����O������C���̌�͕č��Ɏ������ڂ��Ċ���Ȃ����Ă����łł��B�{�Ղ�1980�N���\�B�܂��L���l�ł͂Ȃ����������̂��̂Ȃ���C�A�����W�S���̃W���\���C�쎌�̃��B�g�[���ƁC���Ɍ��������g���I�̕��Ƒ̐����m�����Ă��������̎Y���ł��B���̎����̍�i�͂ǂ���Ƃ��Ă��̂ċȊF���B�{�Ղ���O�ł͂Ȃ��C�Ƃɂ����ُ�ɏo�����ǂ��B�X�e�B�[�r�[�ł��炱���܂ő����Ė�����Ă��Ƃ͖��������B�W���Y�ƃ{�T�m���@��ǂ��Ƃ���肵���ŗǂ̃|�b�v�X�E�E�ƕ����ĐG�肪�������ɁC������āu�ʍ�v�Ȃǂƌ�����l�Ԃ����݂���ł��傤���B�V�˂Ƃ́C�܂��������������l�������̂ł��傤�B�c�O�Ȃ̂́C���t�̐w�e���ǂ��킩��Ƃ����ł����B�����g���I�̎Y�����Ă��ƂŁC�ނ�ȊO�̂��Ƃ͂ǂ��ł��ǂ������̂����m��܂��C������ƕs�e�B���X�p�Ղɂ���EMI���@�����݂ŁC���������w�����x��������������悤���`��B���������� |
 "Introducing the Thinh Nguyen Quartet" (TCB : 24702) "Introducing the Thinh Nguyen Quartet" (TCB : 24702)�@codes: from the underground �ABrooklyn �BFaraos' wrath �Cthe preacher �Ddowntown chaos �Ethen she looked... �Furban lights �Gcodes, pt.2 �Hcodes, pt.3 �Ilove is a strange affair Thinh Nguyen (p) Till Grünewald (sax) Tevfik Kuyas (b) Raphael Ruimy (ds) ���[�_�[�̃V���E�j���[�G���́C�x���������_�Ɋ�������x�g�i���n�B�ڂ����o���͕s���Ȃ܂܂ł����C���t������͂��̃A���g�j�I�E�t�@���I�������ŁC2002�N�ɏo�ꂵ�������g���[�E�W���Y�Ղł́C�N���C�X���[�܂���܂��Ă��܂��B�ނ̃X�^�C���͓`���h�ȍ~�̍��̖z�����I�݂ɏ����������[�h�E�s�A�m�B�_�[�N�ȐF���Ƃǂ������p�����Ƃ肢��C�S���S���Ɛ��ރX�^�C���́C�P�j�[�E�J�[�N�����h�Ɍ����C�Ȃ�قǃP�j�[���u���̗�����p���j�v�ƕ]�����t�@���I���̗�������ނ��̂ł��B���ۋȖ�������Δނ̃��[�c�͈�ڗđR�B�@�Ɂu�u���b�N�v�𑫂��C1980�N��̓`���h�̉�������t�����E�C���g���E�}���T���X�̋P�������G�삪�o�Ă��܂����C�B�ɂ́C�ނɂƂ��Ẵt�@���I�����t���l���Ƃ̈Ӑ}���܂܂�Ă���܂��傤�B�������ɐ�y����l�Ɣ�ׂ�Z�p�I�ɂ͏����ł�����C�Ƃ���ǂ���z���ɉ^�w�Z�I���y�Ȃ�������C�������肱����܂�Ƃ����������������ł����ǁC�����͒�����ւ̎����ƔM�ӂŃJ�o�[�B���т��тƝ��˂�ϔ��q�ƓK�x�Ƀ��J�j�b�N�ȃI�t�r�[�g�Ńe�R���ꂵ�C�V���v���Ȃ��璚�J�ɏ������ꂽ����Ȃ͂ǂ���ǂ������Ă���C�����Ȃ���܂Ƃ܂�̗ǂ��A���T���u�����D��ہB���̌�C2007�N�̌��݂܂Ŗڗ���������͂Ȃ��悤�ł����ǁC������Ɩܑ̂Ȃ��ł����˂��B�T�C�h�����Ŏg���Ȃ�C�[������������Ȃ����Ǝv����ł����ǁH���������� |
 Eric Byrd Trio "Eric Byrd Trio" (Foxhaven : FX-70012) Eric Byrd Trio "Eric Byrd Trio" (Foxhaven : FX-70012)�@taken by force �Aanother time, another place �Bfall of light �Cgoldie �Dunder a blanket of blue �Emaybe baby �Fthe chant �Gwhen you're smiling �Ha WMC autumn �Ijazz thing �Jepilogue: blessed assurance Eric Byrd (p) Bhagwan Khalsa (b) Alphonso Young Jr. (ds) �����̃��[�_�[��1970�N�W���[�W�[�E�V�e�B���܂�B�E�B�����O�{�����Z���o�Đ������[�����h��w�i���}�N�_�j�G����w�j�i�݁C1993�N�ɑ��ƁB���N���瓯�Z�ŋ��ڂ�����Ȃ���2001�N�ɏC�m���܂����B����2001�N�ɃP�l�f�B�E�Z���^�[����W���Y�e�P��g�ɔC������C��ăc�A�[�����s�B���ꂪ�]������C2002�N�ɂ͑��Ɛ����_�܂���܂��Ă���ق��C�N���G�C�e�B�u�����܂Ȃ�w�ȏ܂��x���炤�ȂǁC�n���ł͖��_���X�Ȗ͗l�ł��B���t�ƂƂ��ẮC1990�N����{���`���A�̃e�i�[�����n���[�h�E�o�[���Y�̃R���{�ŃT�C�h�����߂�T��C�E�C���g���E�}���T���X��P�j�[�E�o�����Ƃ��������ʂ����܂����B2007�N�̎��_�Ŕ��\�����A���o���͎O������C�{�Ղ�2002�N�ɏo������B�����e���ł߂�e�i�[�}���̃����E�J�[���Y���C���j�V����Ƀv���f���[�X��S�����Ă���̂����܂����C�܂����t�ƂɐM������Ă���l�q���M���܂��傤�B���[�_�[�̃s�A�m�́C�ŋߖő��ɒ����Ȃ��u���[�X��S�X�y���ɍ��������O���[���B�ȍ��l�s�A�m�B���Ƀ��e���F�̔Z���I���W�i���ɏ���ď���C�Ȃ��p���p�����ƋC�����ǂ��]����J���ҋC���̃s�A�j�Y���ł��B�{�r�[�E�e�B�����Y�ƃ����[�C�E���C�X�̊Ԃɐ��������������C�萔�𑝂₵�������[�h�̖�Y�����悤�Ȗʎ����ƌ����Ηǂ��ł��傤���B�����S�c�S�c�ƒj���ۂ��X�^�C���ł��āC�����炳�܂ɂǂ������͂Ȃ��C������ƌy���ɏ���Ă���������₷���͍D�܂����̈��B���[�J���ȖʁX�̌��E���C���ڔ��ōC�������Ȃ��Z�p�ʂ̃A���������Ă��܂��B�y�Ȃ̓V���v���Ȃ���݂ȗǂ���������Ă���C���[�J���ȃs�A�m�E�g���I�Ƃ��Ă͑����ɏ�o���B����������E��ł����͂��܂��܂��B���������� |
 Dave Peck "Good Road" (Let's Play Stella : LPS 2005-01) Dave Peck "Good Road" (Let's Play Stella : LPS 2005-01)�@yesterdays �Alow key lightly �Bgreen dolphin street �Cthe first song of spring �Djust in time �Ethe star crossed lovers �Fwhat is this thing called love �Gshe was too good to me Dave Peck (p) Jeff Johnson (b) Joe La Barbera (ds) �R�[�j�b�V������ŋ��ڂ�����Ȃ���C�I�X���K�̑n�슈���𑱂��Ă����f�C���E�y�b�N����B�f�r���[�Ղ���n�����y�C���[�V���b�g�z�̍ŗD�G�^������ł͏�A�Ɖ����Ă���C�V�A�g���ɂ͓G�����Ȃ��������Ă���͗l�B�Ƃ��Ƃ��t���[�����X�ł��т�H�ׂ錈�S���Ȃ���C����y�����̐E���̂ĂĂ��܂��܂����B�{�Ղ�2005�N�ɏo����S��B2000�N���\�́w�X���[�E�C���E�����x�ɑ����Ď��g��x�ڂ̃S�[���f���E�C���[(�����̎�)�܂���܂��܂����B���ׂ̍�����ɗ����āC��⎸�s���������@���Ȃ��������C�u�^���̑O��B�Ă̒�C�ނ͓��Ղŏ��߂Ė����ɏI���܂��B���Ȃ��������̂ł��傤�B����͂��ׂ��r���ɐU��ĉ���グ��K�v�̂Ȃ��X�^�W�I�ւƗ����߂�C�A�b�v�E�e���|�ŋZ�ʕs����I�悷����������܂����B�����Ȃ�ƁC�ނ̑Ō��͏[���ɉ~�݂�тт邱�Ƃ��ł��܂����C���ׂ̍����[���C�@�ׂ��ƂȂ��ċP�������߂��܂��B�R���R���ƐS�n�ǂ��]����E��̒P�����ƁC�T���߂Ɉ��Ă���G���@���X�E���C�N�ȃR�[�h�̉����R���r�l�[�V�������߂��Ă��܂����B�x�[�X������L���^�C�v�ɑւ��C�����c�̐U�����キ�Ȃ��������ł��傤�B����ɂ�閳�ӎ��̈��Ă������Ȃ�C�C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ����ΉR�ɂȂ�܂��B����ł��C�ޖ{���̎������͂���������S��C�ق��ƈꑧ�B�C�ȊO�͑S�ăX�^���_�[�h�ȂŌł߁C�}�C�y�[�X�ŏ������C�Ȃ̂����ς�炸�B���������C�����̐g�̏��ق����s�X���[���E�C�Y�E�r���[�e�B�t���t�̃X�^�C�������C�ނ̐^�����B���̐l�ɂ���ȏ�����߂Ă͂����܂��C�ނ��낻��͋��̍����ł����Ȃ��ł��傤�B���������� |
 Jeff Gardner Trio "Abraços" (Terramar : TMAR-0027) Jeff Gardner Trio "Abraços" (Terramar : TMAR-0027)�@chameguenta �Aum abraço na mantiqueira �Bum abraço no Hermeto �Co caminho dos olhos I �Dum abraço no Guinga �Ebarca das estrelas �Fdonateando �Gum abraço no zimbo �Half tones �Io caminho dos olhos II �Jmisteriosa Jeff Gardner (p) Carlos Balla (b) Alberto Continentino (ds) �w�v���C�Y�E�|�[���E�I�[�X�^�[�x�����܂�ɑf�G�ȃA���o�����������̂ŁC�O��Ă��O��Ă��������Ă��܂��K�[�h�i�[����B�p�����y�@���̖ѕ��݂�������C����Ȃ̍˔\�ɂ͍��ꍛ��v���܂��B�h�r���b�V�[�ƃW���r���́u���s�a���g���Őe�a����������v������Ȃ̂��C����h�̊�Ɠ������炢�O���烉�e���E�W���Y�ɂ��X�|�B�C�����̂��Ȃ����n�W���Y�������]���C���ԂɃr�~���[��ᰂ���肻���ȍ�i�����X���\����悤�ɂȂ�܂����B���ă{�T�m���@�Ƃ͂����C�W���Y�I�ɂ͎c�O�Ȃ��牏�ӕ��Ƃ��킴��Ȃ��������B�ŏ����̐��ʂƂȂ����w�X�J�C�E�_���X�x�́C���Ƀ��[�h�t�҂̕n�����ɂ����Ėڂɗ]����̂�����C�o�^�o�^�������Y�������ނ̑@�ׂȃf���J�V�[���Ԃ��C���Ŏc�O�Ɏv�������̂ł��B�{�Ղ͂��ꂩ��W�N���o���C����Ȃ��u���W���^���ՁB������݂̂Ȃ������n�l���}�����g���I�Ґ��ŁC���ӂ̎O�A���t�@���Ă���ɂ������e���E�W���Y�������߂܂��B�������O�N�C�w�E�E�I�[�X�^�[�x�𐁂��������̘^���B����Ȃ̏o���Ɋւ��Ă͕���Ȃ��̃n�C���x���B�n�������������錻�n�̃t�����g�������Ȃ������̂��t�����Ă���C�܂Ƃ܂�̗ǂ��͉ߋ��̎���̑唼���y�X�Ə����Ă���̂ł́B�Ƃ��낪�ł��˂��E�E�v��̔O�Ƃ͗����ɁC�ނ̃s�A�j�Y�������e���E�r�[�g�Ƃ܂�ō���Ȃ���ł���B���ӂ̎O�A���𑽗p�����L���L���E�s�A�m�́C�K���I�ŏc�̐U���̂Ȃ��{�b�T���̂����ł͂܂Ȕ̌�B���Ԃ̖R�������Y���̂��A�ʼnA�e��������t���[�Y�C���ƂȂ�C�����̖��ł����ւ��Ď�ȗ��݂̊�p�n�R�ɋ����Ă��܂��B�Ȃ܂��y�Ȃ��ǂ������ɁC�u�C�~�y���̏�Ȃ��B���߂�NY�̘r���������t��������C�����������Ԃ��āC�ނɑŌ����ۂ��e���]�T��������ꂽ��ł��傤���E�E�B���ɖܑ̂Ȃ��B�������� |
 Klaus Ignatzek Group "Day for Night" (Nabel : 4639) Klaus Ignatzek Group "Day for Night" (Nabel : 4639)�@day for night �Athree wishes �Bnew surprise �Cbeautiful colours �Dblue energy �Eballad for Ulli �FMonks visit Klaus Ignatzek (p) Joe Henderson (ts) Jean Louis Rassinfosse (b) Joris Dudli (ds) �Ђƍ��b����ĂтȂ���C�ŋ߂��܂薼�O���Ȃ��Ȃ����C�̂���h�C�c�̃o�b�v�D���C�O�i�c�F�N�́C1954�N�E�B���w�����V���[�x�����܂�B�o�b�v�̃C���[�W�������̂ł����C���̓I���f���x���N����o���̂��C�`���b�N�E�}���[�j�N�ɒ�q����B����ɁC�ꎞ�̓U���c�u���N�̃��[�c�@���e�E�����y�@�Ńn�[�r�[�̎w�������o�����B�{�^���̂̂��C�x�[�X�̃}�[�e�B���E�E�C���h�ƍ������d�t�Ղł́C�т����肷��قǃ����J���ȃs�A�m���I���Ă��܂����B�����ċZ�I�h�ł͂Ȃ����̂̃I�[�����E���h�Ɉ�ʂ肱�Ȃ���쒀�͓I�ȘȂ܂��́C���̕ӂ�ɏ��Ȃ������ł��傤�B1989�N�^���̖{�Ղ́C�ފ݂���W���[�w�����}���CEU���ŏ����������B�Ȃ��ɃW���[�w�����H�̂킯�́C��傪10���Ԃɓn���ăh�C�c�ł����Ȃ������t���s�B�S�Ȃ����삵���C�O�i�c�F�N������z�t�ƂȂ�C�L�O�B�e�I�ȈӖ������ł̘^���������悤�ł��B�̂��N���X�E�N���X�ň���g����x�[���}�����^����S���B���łɂ��̍�����o�b�v�D�����݂��̈��͂ŏW�܂��Ă��Ă���͖̂ʔ����Ƃ��������Ƃ������B�����͂݁C�g���ȕ��͋C�Ř^��ꂽ�̂��t���B�Ƃ��ɂ��������F�ڂ��g�����[�_�[���C����܂łɂȂ��f����࣏n���o�b�v�E�C�f�B�I���ɓO���Ă���D�܂����ł��B���ς�炸��łɎg�����T���t�H�b�Z�̂��x�[�X�́C����ς�d�����̃��[�_�[�Ƃ͍���Ȃ��C�����܂����C�I�����@�[�E�P���g�ŊJ�Ԃ��鑾�ۂ������ו��̃j���A���X���e�����B���ӂ��C���̉��t�́C���˂�悤�ɂ��Ȃ₩�ȃW���[�w���̎�������[���x������Ȃ����ǂ��������Y���B���Y���������������������肵�Ă���C�i�i�ɗǂ��o����������ł����E�E�B����ł��C�ߋ��ɒ������ނ̃��[�_�[�Ղ̂Ȃ��ł́C���炭��ԗǂ��܂Ƃ܂����D�Ղł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������� |
 Jef Neve Trio "Nobody is Illegal" (Universal : 06025 1716747
6) Jef Neve Trio "Nobody is Illegal" (Universal : 06025 1716747
6)�@airplane �Anothing but a casablanca turtle slideshow dinner �Babschied �Castra �Dnobody is illegal �Eunprepared �Fsecond love �Ggoldfish �Htogether at last �Iuntil now �Jdelayed Jef Neve (p) Piet Verbist (b) Teun Verbruggen (ds) Hans Verhilst, Simon Haspeslag (hrn) Fredrik Heiman, Pieter Kindt (tb) Berlinde Deman (tba) Nicolas Kummert (ts) 1977�N���܂�̃��[�_�[�́C���[�����X���y�@�Ń����h�[�N�̌O�����x���M�[�l�B2000�N�̑��ƌ�C�N���E���E�f�Ȃ鎺���y�A���T���u���𗦂��Ċ�������ȂǃN���V�b�N�ɂ��͂����C�����g���Ŋ������ł��B����w�C�b�c�E�S�[���x�͕ꍑ�̃W���Y�E�`���[�g�ň�ʂɂȂ�ȂǁC�����ł͂��Ȃ���悢�悤�ŁC���ꂪ�]�����ꂽ�̂�2006�N�x�̃t�����h���̏��E���y�Ƌ���iZAMU�j�܂̃W���Y�������܂��܂����B�{�Ղ̓��j�o�[�T���ֈڐЂ��č�������[�_�[��O��B���ǂT�{������������y�A���T���u�����R�ȁC�A���N�V�E�g�D�I�}�����l�d�t�c�Ńn�[�h�{�C���h�ȉ��F���o���Ă����j�R���X�E�N�������g���}���ẴJ���e�b�g���t���R�ȉ����C�g���I���t�͎c��T�Ȃł��B�g���I�ł̓X���F���\���E�g���I��o�b�h�E�v���X��Ɠ��l�C�G�t�F�N�^�[��ʂ��č������C���܂����C�`�������ɕϔ��q�Ɨ���e���ɂ�郁���h�[���̇@����C�����q���ق��X�^���_�[�h�������h�[�̃A�����W�Œ����H�Ɏ���܂ŁC�j�ƂȂ�̂͌h�����邨�t���l�̃s�A�j�Y���B�Ȏv��̔O���C�W���Y���t�ƂƂ��Ă̔ނ̈ꗢ�˂Ȃ̂ł��傤�B�ǂ��������I�u���K�[�h��t���邻�̌�̐��Ȃ́C�ǂ����������N���V�b�N�Ƃ̗����Ŋ������郊�[�_�[�̃L�����N�^�[���F�Z���o�����ʂ�ⓝ�ꊴ�Ȃ����ʂɂ��Ȃ��Ă���C�t���̌|�������̂܂܂Ȃ������ӏ��́C���̂����|���܂Ƃߐ�ʎt���̂��Y�݂܂œ��P���Ă���B�����h�Ƃ��������h�B�蕨�̃W�����}���ǂ����W�I�ɉ�������̂����C����ȍ~�̒����ǂ���E�E�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤�B�������� |
 Christoph Stiefel "7 Meilen Stiefel" (Neu Klang : NCD4009) Christoph Stiefel "7 Meilen Stiefel" (Neu Klang : NCD4009)�@seeking solid ground �Adistant beauty �B7 meilen stiefel �Cstill �Dcontinuum �Eojémineh �FNina �Gthe girl from Ipanema �Hthe boy from Ipanema �Icaravan �Jhome Christoph Stiefel (p) Patrice Moret (b) Marcel Papaux (ts) 1961�N�`���[���q���܂�̃X�e�B�[�t�F���́C10�N�O�ɏo���\������w�X�E�B�[�g�E�p���h�b�N�X�x�ŁC�N��Ȉ�ۂ��c�����e�B�G���[�E�����O���̃s�A�m�e���B�k�������Ì��ɂ����悤�Șa�����o�ƁC��}�ȍ�ȗ͂����s�A�j�Y���ŁC�ꎞ�͂���Ȃ�ɘb����Ă��̂ł����B�`���J�|�R���l�A�[�X�L���������Ȃ��J���Ńl�W���ɂ߂Ă������߁C���݉������ɍς�ł��܂������C�ނ͌��\�C���y��������l���Ă����̂悤�ŁB�t���[��g�[���E�N���X�^�[�C�����t�@�����p���ĕ����L�����̂����ߔ����C����ł͔h��ɑ�R�P���Ă��܂��܂����B���ẴE�C���g�����Ȃ���C�ނ͗����̖ʔ����Œ������鎎�݂肸�ɑ����Ă���͗l�B�H���@�A�B�I�̂S�Ȃ͓����s�A�C�\���Y���t�A�v���[�`�Ȃ闝�_�Ɋ�Â��Ă���Ƃ��B�A���X�E�m���@�Ɍ������R�����闝���Ȃ̂��E�E�����͐��Ȃ����Ă����܂��B���������̎v�f���C�p���Ĕނ̉��y�������ɂ��Ă��܂��Ă���͔̂���Ƃ������c�O�Ƃ������B�w�X�C�[�g�E�p���h�b�N�X�x�̕W��ƁC������S�������|�����Y�~�b�N�ȕϔ��q�`���[���̇B�͂܂��ɂ��̏؍��B�����A�v���[�`�䂦�ɁC����ɂ��A�[�X�L���̖��҂��ꖇ������Ȃ��Ƃ��I�悵�Ă��܂��B�����܂ŃK�`�K�`�ɍd�����y�����̂Ȃ�C���߂đ����͂��̊k���������˂��j�邭�炢���C�ɖ����Ă��Ȃ���B�W���Y�ł���ȏ�C�P�Ȃ铪�ł������̋����ȉ��y�ł����Ȃ��Ȃ�ł��傤�B�O��ł����ۂɕ�����������L��������܂����C�{�Ղł��J��Ԃ��܂��傤�B�����������Ƀp�|�[�ł͗͗ʕs���B���ƁC������ƍl�������̎���L����������Ȃ��ł����˂��H�����ċC�������Ă���킯�ł͂Ȃ��C������i�ł͂Ȃ������ɁC���Ƃ������ʊu�C�~�y�̊����@���܂���ł����B�������� |
 Michael Davis "Trumpets Eleven" (Hip-Bone Music : M105) Michael Davis "Trumpets Eleven" (Hip-Bone Music : M105)�@permit required �Ac to z �Bblue day �Cbrass walk �Dzona �ESan Jose �Fbig city �Gcole henry �Hschapa �Ifamily tree Michael Davis (tb) Eddie Henderson, Randy Brecker, Phil Smith, Chris Botti, Ryan Kisor, Bobby Shew, Scott Wendholt, Malcolm McNab, Tom Harrell, Chck Findley, Jim Hynes (tp) Alan Pasqua, Phil Markowitz (p) Dave Carpenter, Jay Anderson (b) Will Kennedy, Adam Nussbaum, Jeff Ballad (ds) ���炭���[�_�[�Ղ��̂͏��߂ĂƎv����}�C�P���E�f�C���B�X�́C�J���t�H���j�A�B�T���z�Z�o�g�̂ڂ�Ƃ됁������ȉƁB�C�[�X�g�}������𑲋Ƃ����̂��C�o�f�B�E���b�`�y�c���o�ăt�����N�E�V�i�g����[�����O�E�X�g�[���Y�C�X�e�B���O�Ȃǂ̃o�b�N�E�o���h��n������C�y�c�����L�x�ł��B�ǂ��炩�Ƃ����Ɖ��������^�C�v�ł͂Ȃ��ނ��C�o���ɗ��ł����ꂽ��ҋȂɂ͂���Ȃ�̎��M������悤�ŁC����̃��[�x���y�q�b�v�{�[���z�����_��8���̃��[�_�[�Ղ\�B������w�T�C�h�E�H�[�N�E�J�t�F�x�́C�S�ă��W�I�ǂ̃G�A�v���C�E�`���[�g�Ńg�b�v20�ɓ����������ȁB�{�Ղ�2003�N�ɏo��8���ڂŁC�W��ɂ���ʂ胉�b�p����11�l���Q����������B�Ƃ͂����C�A���o�����X��12�ǂŐ��t����̂ł͂Ȃ��C�Ȃ��Ƃ�1�C2�l�̃��b�p���������ĂāC����͌���4�l���t�ɓO���鉜�䂩��������ł��B���Y�����̓��[�_���ȃ}���R���B�b�c�`�A���_�[�\���`�o���[�h�̃g���I�ƁC�s�[�^�[�E�A�[�X�L�����E�B���E�P�l�f�B�ɑ������o�b�h�����Y�Q���ɂ��g���I�̂Q�`�[���ƂȂ��Ȃ��ɍ��B�P�l�f�B�Ƃ����C�G���[�W���P�b�c�ȂW�r�[�g���̇A�ŁC�p�X�J�̃��[�h�e�����{�ƃt�F�����e���y�X����B�����B�`���Ńj���[���[�N�E�t�B���̎�ȃt�B���E�X�~�X�����C�������N���V�b�N�ƚX�炸�ɂ͒����ʐ��ݐ����n�C�E�m�[�g�ȂǁC���ґ����ʼn��t���̂̃��x���͏[���ɍ����ł��B���ꂾ���ɐɂ����̂́C���{�l�̍�Ȃ����ЂƂ喡�Ȃ��ƁB���Y�������t�ł郊�Y���ƃR�[�h�̕��R���ɔ䂵�āC���t��̂̎���������������C���̔��t���������ďd������ł��܂��̂̓r�b�O�E�o���h�o�g�҂̐��H�R���{�E�W���Y�̂���Ə�����a���������o���Ă���ܑ͖̂̂Ȃ������ł��˂��B�������� |
 Cyrus Chestnut "Earth Stories" (Atlantic : 82876-2) Cyrus Chestnut "Earth Stories" (Atlantic : 82876-2)�@decisions, decisions �Agrandmama's blues �Bmy song in the night �Cnutman's invention#1 �Dblues from the east �Ecooldaddy's perspective* �FMaria's folly �Geast of the sun and west of the moon �HGomez �Iwhoopi �Jin the garden Cyrus Chestnut (p) Steve Kirby (b) Alvester Garnett (ds) Eddie Allen* (tp) Steven Carrington* (ts) Antonio Hart* (as) �N�����Ă�����ǂ��Ƃ͎v���ʁC�S�Ɋ��ꂽ�]�V�W���P�b�g�̓T�C���X�E�`�F�X�i�b�g�̃A�g�����e�B�b�N��O��Ƃ��āC1996�N�ɔ��\�B�ނ�1985�N�Ƀo�[�N���[���y�@�i�݂܂����C����܂ł͌̋��{���`���A�̃}�E���g�E�J���K���[�E�o�v�e�B�X�g����Ńs�A�m���t�߂Ă���C�؋�����̃S�X�y���[�Y�B���̍��X�����n�̕������C���C�E�u���C�A���g���V�̃A���y�W�I�ŃI�u���[�g�ɕ�����ȃs�A�j�Y�����C���̐l�̖��͂̑傫�ȕ������߂Ă���܂��傤�B�ނ̕]������߂��̂��C���B���b�W�E���H�C�X���Ŕ�]�Ə܂���������w�����F���C�V�����x�Ȃ̂͋��炭������٘_���Ȃ����Ƃł��傤���C���̌�̔ނ��w�����F���C�V�����x�������ʂ����ʂ܂܁C�����Ɏ����Ă���͉̂����Ƃ��������Ƃ������B���ꂾ�����̃A���o���́C�ނɂƂ��Ă��_�̗̈�ɓ��ݍ��u�Ԃ̍��������イ���ƂȂ�ł��傤�B�ނ̃��[�_�[�Ղ͏��Ȃ��炸�������Ǝv���܂�����ǁC�Z�I�h�ł͂Ȃ����ɉ��ł�����p�ɂ��Ȃ����̍L�����Ђ����邱�Ƃ������悤�ŁB���鎞�͕��s�����ȃ}�b�R�C���ǂ��ɑ����ă~�X�^�b�`�̏��R�����C����Ƃ��̓R�e�R�e�̃S�X�y�����Ȃ����W���Y�E�t�H�[�}�b�g�ʼn����ă��C���X�g���[���E�W���Y�D�����h��������������ƁC��ѐ�������悤�Ŗ����������Ă���悤�ł��˂��B�{�Ղ͂�����̍ō����삩��O�N��̍�B�E�������S�Ă��g���I���t�Ƃ������ƂŁC���Ȃ���҂��̍w���ł����B��╝���L�������C��������܂Ƃ܂�Ɍ����܂����C�}�b�V�u�C���Ŏ��ł�����C�S�X�y���ɔh��ɓ]��͗�ɂ���ė�̔@�����B����ł��C�[���ɘe���ɃX�C���O�����C���C�E�u���C�A���g�͂����̃R���R���|�����삷��@�C�F�C�G�͂������B��������ŁC�e�̓��w�����F���C�V�����x���̘r������������C���Ȃ��Ƃ���L�̂R�Ȃ��炢�͍K���ȏu�Ԃ��K�ꂽ�ł��傤�B�e�̍��������C�y�����瑫�����̂��Ă��܂����B��ׂ邪�̂��ґ�ł����C�ɂ������Ƃł��B�������� |
 Mike Longo "New York '78" (Consolidated Artists Productions :
CAP915) Mike Longo "New York '78" (Consolidated Artists Productions :
CAP915)�@New York '78 �Athe party �Bsand in your blues �Ca point beyond �Ddown under �Ekeep searchin' Mike Longo (p, ep) Randy Brecker, Jon Faddis (tp) Junior Cook, Bob Mintzer (ts) Slide Hampton, Curtis Fuller (tb) George davis (g) Bob Cranshaw (eb) David Lee (ds) Steve Kroon (cga, perc) Ben Aronov, John Hicks (synth, clvn) �捠�o���g���I��w�X�e�B���E�X�C���M���x�Ō��݂��������x�e�����C�}�C�N�E�����S����B1939�N�V���V�i�e�B�ɐ��܂ꂽ�ނ́C���P���^�b�L�[��w���o�ăv������B���ł������O�����Ƃ͖ő��ɂȂ��ނ��C���̓R�[���}���E�z�[�L���X�̃T�C�h�������o�āC1966�N����1973�N�܂ł̒����ɓn��f�B�W�[�E�M���X�s�[�̘e���ł߂���m�B�����̒ʂ�R��S�ނ��^���̕��e�ŁC�f�J���������̂��ɒB���Ⴒ�����܂���B������W�܂��Ă����ʁX���C������ƐM���������قǍ��B���t�̏o���̈����낤�͂����Ȃ��C�����e���ł߂Ă������f�B�W�[�̉��y����@���ɔ��f���C�����Ƃ��Ă͍ł��������ȓs��̃��[�h�����ɂ����C�[���̑�^�R���{��ɂȂ��Ă���B�S�҂ɃR���K�ƃp�[�J�b�V��������C�S�����͊F���B���ɃN�����B�l�b�g������C�x�[�X�͂���̒ʓd�B�����M�a���C�����̓����ɏے������1970�N��̏L�݂����Ղ�̃W���Y�E�t�@���N�ɒ�R���Ȃ���C�B�ꂽ�D���e��Ƃ��Ėʔ���������̂ł́B�Ƃ������Ƃł��E�߂ł��邩�ǂ����́C�w�Y���R�����{�x��w�`���[���[�Y�E�G���W�F���i�����C�N�̂��Ⴀ��܂����w�j�x�C�w�o�C�I�j�b�N�E�W�F�~�[�x������Ŋ|�����Ă����ȁC�������]���̃A�t���E�L���[�o���ȁi�����̓��e�����́j���p����������邩�ɂ������Ă���܂��傤�B���ƂȂ��Ă͉��Ƃ����g���ł����ǁC�d���������Ȃ����[�_�[�̃V���O���E�g�[���ƃE�j�������N�����B�l�b�g�����C�ǂ��ƂȂ��̂̃W���[�E�T���v����X�e�B�[�r�[�݂����B�Ƃ������Ƃ͓d���n�[�r�[�ۂ��ƌ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��킯�ŁB�킽�����I�ɂ�B���t�@���N��Ƃ��āC�[���u����v�ł��B�������� |
 David Newton "Return Journey" (Lynn : AKD 025) David Newton "Return Journey" (Lynn : AKD 025)�@stolen time �Aonly passing through �Bwhile you're away �Con the holizon �Dhome from home �Ereturn journey: on my own �Fon the road �Ginto somewhere �Hgone forever David Newton (piano) �a�m�̂悤�Ɋi�������s�A�m��炷���ƂɊ|���ẮC���炭�p���ł��g�b�v�E���x���ł͂Ȃ����Ǝv����f���B�b�h�E�j���[�g���B�������邽�тɁC���肪�o�Ă��܂��܂��B�ӊO�ɂ��L�����A�̏o���_�̓o�f�B�E�f�t�����R�̃T�C�h�����B�e�f�B�E�E�B���\����W���[�W�E�V�A�����O��̒��Ԕh�I�G���K���X�������ə����s�A�m�́C�N�G���̂������킯�ł��B�{�Ղ�1994�N�ɏo���R���ڂ̃��[�_�[��ŁC���g���߂ăs�A�m�Ƒt�����݂����쎩���ՁB�ނ́C�{�Ք��\����O�N��ɂ��w12��12���x�Ƒ肷��s�A�m�Ƒt�Ղ���邱�ƂɂȂ�܂��B���Ղ��V�i�g���䂩��̃X�^���_�[�h���W�߂Ă����̂ɑ��C������͑S�Ȃ�����B���̂Ԃ�ނ̎����y�����F�Z���o�Ă���_���C�傫�Ȗ��͂Ƃ����܂��傤�B�ނ̃s�A�m�́C�G���@���X�I�ȑ@�ׂ���a���̂͂����ɐD��������C�X�g���C�h�t�@����g�����Õ��Ȍ������x�[�X�B�����������̃X�g���C�h���l�̃��Y���E�p�^�[���ƍT���߂ȃG���K���X�̂䂦�ɁC�ǂ������Ă���⎗���悤�ȋȒ��ƂȂ�C�ŋC����������Ƃ����̂��C�E�B���_���E�q���I�Ȉ���������̖������ۂ߂Ȃ����炢������܂��B�������C�������Ƀ^�b�`�̔������Ɩ������͂�����̋u�^���Q�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǂɏ�B���Y�킩���n���ɂ܂Ƃ܂����C�ǂ������D��U���I���W�i���́C�ǂ���g�[���E�|�G���I�Ȏ�ƃf���J�V�[������C�ǂ��Ӗ��Łu��l��BGM�v�ƌĂт����Ȃ�܂��B�V���A�Ȑl�ł��˂��B���Ԃ�ނ́C�����\���E�s�A�m�Ղ�����Ă�����Ȋ����Ɏd�オ�����Ⴄ���Ƃł��傤�B�������� |
| Other Discs |
 Nnenna Freelon "Listen" (Columbia : CK 64323) Nnenna Freelon "Listen" (Columbia : CK 64323)�@Gaia's garden �Adad's delight �Bwill you still love me tomorrow �CI'll be around �Dballad for Aisha �Ea hundred dreams from now �Fcircle song �Gsol cycle �Hwaste not want not �Ijourney of the heart �Jsong of silent footprints �Klost in the stars �Llisten Nnenna Freelon (vo) Bill Anschell, Bill O'Connell (p) Avishai Cohen, Ron Carter (b) Cecil Bridgewater (flh) Bill Fischer (vib, mba, bells) Alex Foster (ts) Earl Gardner (tp) Kathryn Kienke, Julien Barber (vla) Yusef Lateef, Dave Valentin (fl) Earl McIntyre (b-tb) Eugene Moye, John Reed (vc) Dick Oatts (as, ss) Stan Pollack, George Wozniak, Richard Hendrickson (vln) Scott Sawyer (g) Ricky Sebastian (ds) Warren Smith (perc) Scott Whitfield (tb) 1954�N�}�T�`���[�Z�b�c�B�P���u���b�W���܂�̏����̎�j�[�i�E�t���[�������C1994�N�ɔ��\������O����E���܂����B��������̂ɋ����������������̂́C�V�����Y��w���o��܂ʼn��y�Ƃ͂قƂ�ǐړ_�������C�q�ǂ��O�l������ăt�c�[�̐����𑗂��Ă��������ȁB����Ȕޏ����W���Y�ֈ������̂��C�{�Ղɂ��Q�����Ă��郆�[�t�E���e�B�[�t�B���̌�C����܂��{�Ղɂ��Q�����Ă���r���E�A���V�F����ƃg���I��g��Ŋ������n�߂��ޏ��́C�G���X�E�}���T���X�Ɍ��o����ē��p��\���C1992�N�ɏ����[�_�[��\�B���݂܂�10���قǂ��R���X�^���g�ɐς݂����C�̂��r���[�E�z���f�B�܂Ȃ�̏��܂���܂��������ȁB�\����Ȃ��C�S�R�m��܂���ł����E�E�B�ޏ��̓f�r���[�����C�T���E���H�[���̃p�N�����Ə�����C���������������ŁC�m���ɃX�L���b�g�̑f���ڋ��ȉ����O����h�X�̗��������Ղ�͈ӎ����Ă���Ƃ��낪���Ȃ��炸�B�������C����I�ɈႤ�̂��A�̑����ł��傤�B���ʂ��R�������߁C�T���̍ő�̖��͂ł��������������I�ɕs�����Ă��܂���C�̂����L�т���X�����Ȃ�C�����I�ȃR�u�V���P�Ȃ鉹���̃R���g���[���s���ɕ������Ă��܂��B�^�������n���Ƃ͂����C�y�Ȃ͂܂��܂���������Ă��܂����C�������f�B�b�N�E�I�[�c�̑f���炵���T�b�N�X���j�����C���t������Ȃ�ɏ��Ă��邾���ɁC�̐S�̃��H�[�J�������ア�͎̂c�O�ł��˂��E�E�B�t�@���̕��\����Ȃ��B���ɂ��O���~�[�ɂU�x�m�~�l�[�g����Ă���l�ւ���ȕ]�������������Ȃ��āB������ |
 Ted Curson "Pop Wine" (Futura : GER 26) Ted Curson "Pop Wine" (Futura : GER 26)�@quartier latin �Aflip top �Bpop wine �CL.S.D. takes a holiday �Dlonely one Ted Curson (tp, pcl-tp) Georges Arvanitas (p) Jacky Samson (b) Charles Saudrais (ds) 1935�N�t�B���f���t�B�A�o�g�̔ނ͂T�˂ŃT�b�N�X�𐁂��n�߁C10�˂Ń��b�p�ɓ]���B���n�̃O���m�t���y�@�Ŋw�̂��C�j���[���[�N�֏o�ăW�����E�R�X�e���Ɏt���B�`���[���[�E���F���`�����̃O���[�v�Ńv�������C���Ȃ��}�C���X�Ɍ����߂��C1959�N�ɂ̓~���K�X�̃O���[�v�։������Ĉ�C�ɒm���x�A�b�v�B�����œ��m�n�̐�s�W���Y�����ƒ��ǂ��Ȃ����ނ́C�t���[�̔M�C�ƃ|�X�g�E�o�b�v�̂ǂ�ǂ늴���I���ܒ������X�^�C��������C�h���t�B�̌��ǂ��悤�ɁC�����Ή��B�Ƃ̊Ԃ��s���߂���Ȃ��牉�t������W�J���Ă����܂��B�{�Ղ����̍D��ŁC1971�N�p���^���B���傤�Ǔ������[�h�E�s�A�m�ւƒE�炵�Ď��͂����������W�����W���E�A�����@�j�^���]���C�t���[�L�̃��������Y���̗͔h�W���Y������Ă܂��B�A�����@�j�^�̓��[�h�ƑO�q���ł���悤�ɂȂ����̂��]�������������̂��C13������@�ł͎����H������ɍ����^�w���J��o���C�N���X�^�[�a�����K���K���@���ĉ��C�����グ���ł����ǁC����炪���ЂƂ������B�E��̉�]���݂ŋ}���������̂ŁC�ǂ����Ă��Ō��͐j�̔@���ׂ��_�o���ɂȂ�C���E�̎�͘a���ƒP�����ɕ������Ă��܂��C���܂��ɂ��̍���̘a�������R�Ȃ��߁C��������Y�ݗ��Ƃ����M�C���㊊�肵�Ă��܂��B�����փJ�[�\���̂������ɂ��Z�I�h�Ƃ͌�������b�p�������ł�����C�C�������摖���ۂ�@���܂���B�W���Y�͋C�������ȕ��͗������������ł��傤���ǁC�̐S�̘r���[���ɔ���Ȃ���ł͖{���]�|�B�������ċ}�����ɂ���ł��ǂ������̂ɁE�E�B�Ƃ����킯�ŁC���̎���Ȃ��̋C�ɂȂ邠�����́C���ЂƂ��������܂���ł����B�ڗ��͇̂@�Ȃ�ł��傤���C�l�I�ɂ͌��̃h���h�������o���b�h�̂ق����u�炵���v�ł����C���t���܂Ƃ܂��Ă���C���������܂��B�������� |
 Curt Smith "Soul on Board" (Vertigo-Phonogram : PHCR-1216) Curt Smith "Soul on Board" (Vertigo-Phonogram : PHCR-1216)�@soul on board �Acalling out �Bbeautiful to me �Cwonder child �Dwords �EI will be there �Fno one knows your name �Grain �Hcome the revolution �Istill in love with you Curt Smith (vo, g, b) Jimmy Copley, Steve Ferrone (ds) Neil Taylor, Colin Woore (g) Martin Page, Alan Kamaii (b) Carol Steele, Paulhino Da Costa (perc) Billy Livsey, Martin Page, kevin Deane, P.J.Moore, Jeff Bova, Kim Bullard (key) et al. ���ꂾ���f���炵���A���o�������Ȃ���C1991�N�Ɂy�e�B�A�[�Y�E�t�H�[�E�t�B�A�[�Y�z�̕Њ���I�[�U�o���ƌ��ܕʂꂵ�Ă��܂����J�[�g�E�X�~�X�B�f�r���[�삾�����w�U�E�n�[�e�B���O�x�ł́C�V���O���̑S�ĂŃ��[�h�E���H�[�J����S�����Ă����ɂ�������炸�C���̌�O���[�v�̕��������V���A�X�ɂȂ�ɂ�C���X�Ƀx�[�X�t�҂Ƃ��Ă̖����Ɉ͂����܂�Ă����܂����B�s�����������̂����m��܂���B���Ԃ�����������C���[�����h���^���͖ق��Č��܂���ł������C���Ǘ��R�͕������܂�܂ł��傤����ǁC���ꂪ������Ȃ��E�E�Ȃ�Ďv���Ă�t�@�������Ȃ��Ȃ���Ȃ��ł��傤���B�{�Ղ̓O���[�v�𗣂ꂽ�ނ��C1993�N�ɍ�����\�����`�̑��e�B�������C�{���ł͂قƂ�ǔ���Ȃ�����������C�č��ł̓����[�X���炳�ꂸ�C����R�����肾������i�ł��B�d�オ��́C�w�V���E�g�x�̉����@�ނŁw�U�E�n�[�e�B���O�x����蒼�����悤�Ȋ����B�X�e�B���O���̓��Ȑ���������Ă���̂́C�w�V�[�Y�E�I�u�E�����x�ւ̋��D�������̂����m��܂���B�p���炵���m�[�u���ȓ�����������������́C�₩�o�̔�����|�b�v�E�o���h�Ƃ͂ЂƖ��Ⴂ�C�������Ǝv�����ʁC���ƌ����܂����Ȃ��ǂ��ɂ������ŁE�E�i��j�B�e�X�̌��Ă͌����Ĉ����Ȃ��ɂ�������炸�C�I�[�U�o���ɔ�׃l�A�J�ōS��̂Ȃ��ނ̎p�����C�y�Ȃ̒ǂ����ݕs���ɂ��̂܂ܔ��f����Ă��Đɂ����̈��B���ǂ��̌�w�݂�ȃn�b�s�[�G���h����D���x�ōČ����H����������Ƃ�������Ă��C���̂Q�l�͎Ԃ̗��ցB�ǂ����������Ă��̈�ȂȂ��E�E�B�������܂������������v��ꂽ����ł��B������ |
�i2007. 9. 1�j
�E�e�F2007�N9��1�� 2:50:41
 �����֖߂� |
����20�_�C����10�_�Ō��Ă�������
| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||
